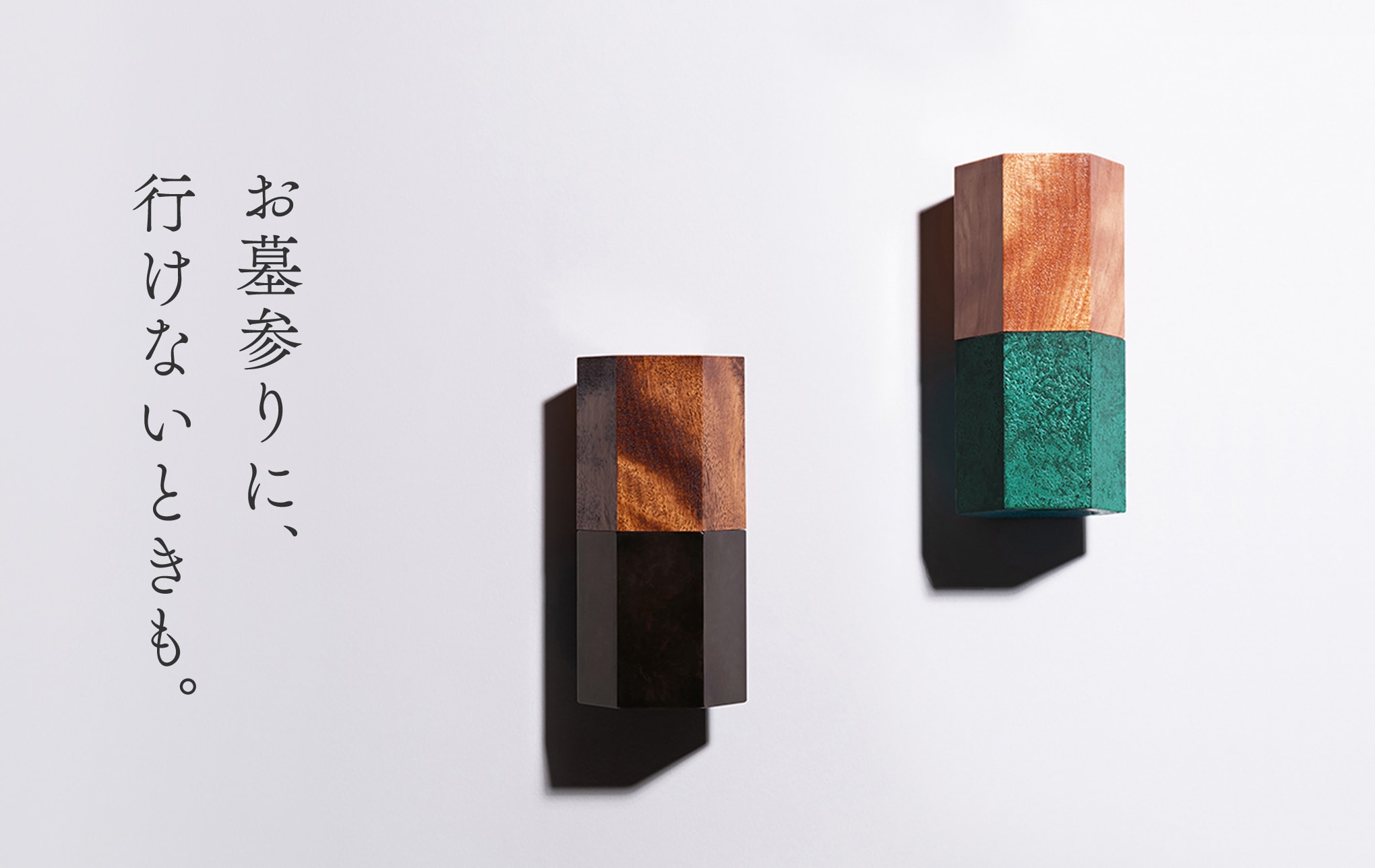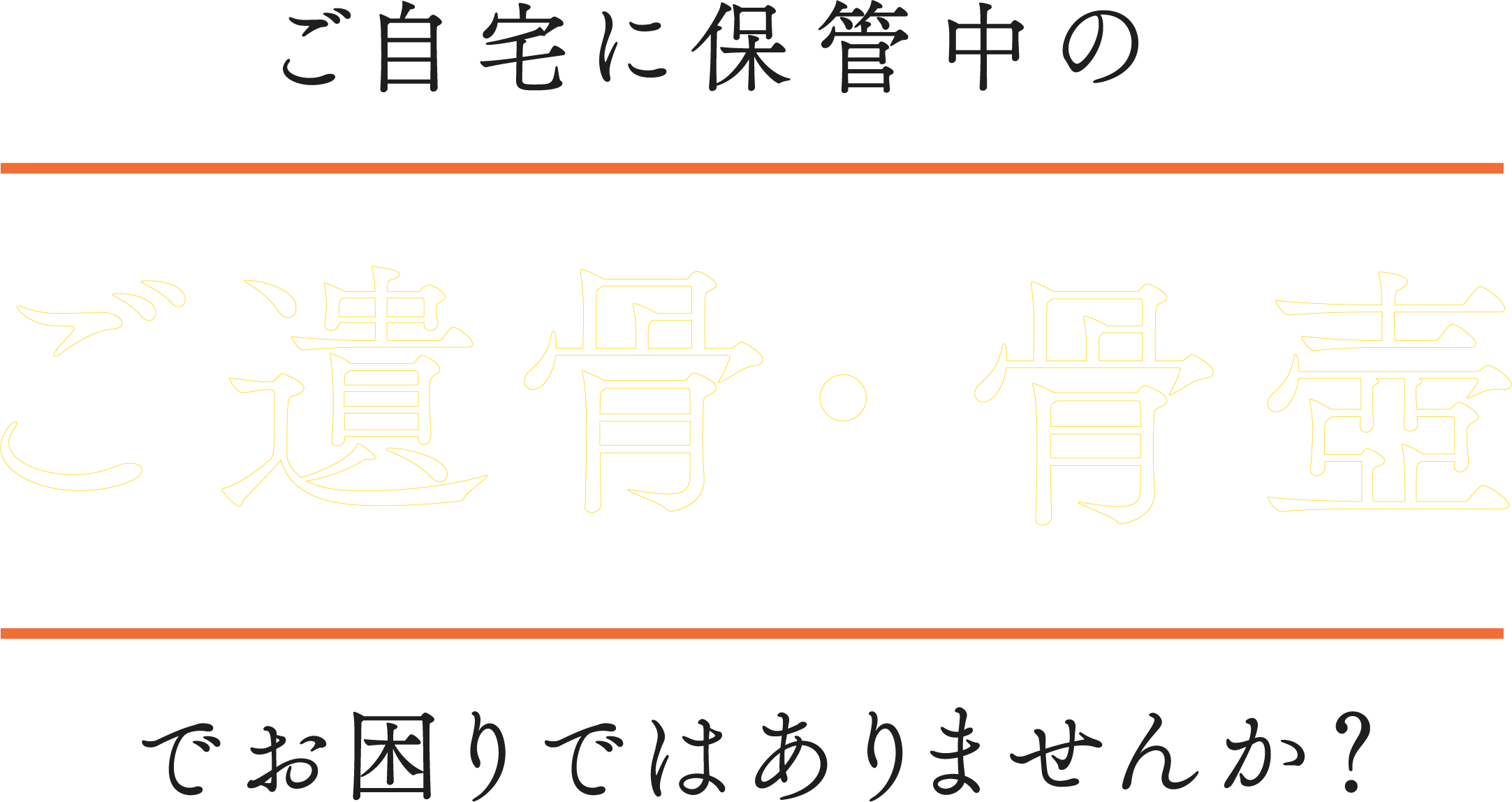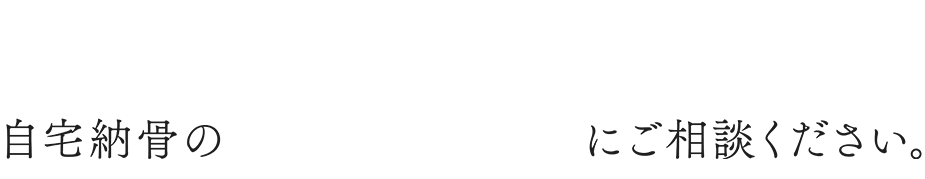「死んだらどうなるのか、死ぬということがどういうことかわかっている人はいない。しかし、それは生きていることもわかっていない、ということです」と話すのは、社会学者の橋爪大三郎さんだ。
平和で豊かな社会では、死に直面するのは自分が死ぬときだけで、生き死にについて考える機会はほとんどない。しかし、死を考えることは、よりよく生きることを考えること、だという。
特定の信仰をもっていない人間にとっては、宗教というと「信仰」「経典」「教義」「お布施」といった言葉が思い浮かび、ずいぶんハードルが高いものに感じる。しかし宗教とは、今まで人類が積み重ねてきた人間や世界についての考え方であり、そこには多くの知恵が詰まっている。キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、儒教、仏教の五大宗教は、人間は死んだらどうなると考えてきたのか。宗教を手がかりにして、私たちはもっと自由に、生と死、人生について考えてもいいのではないか。その背中を押してくれるのが本書『死の講義』(ダイヤモンド社)だ。著者の橋爪大三郎さんに話を聞いた。
(インタビュー日:2021年1月27日、聞き手:長野光 シード・プランニング 研究員、構成:SOBANI編集部 添田愛沙)
本記事はこちらの動画インタビューのダイジェスト記事になります。動画もぜひご覧ください。

プロフィール
橋爪 大三郎(はしづめ・だいさぶろう)
1948年生まれ。社会学者。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。
大学院大学至善館教授、東京工業大学名誉教授。
著書に『はじめての構造主義』『はじめての言語ゲーム』(ともに講談社現代新書)、社会学者・大澤真幸氏との共著に、『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書、新書大賞2012を受賞)などがある。(このプロフィールは本書籍が刊行された時点のものです)
[本文]
――本書では、世界五大宗教の基本的な構造をもとに「世界は、宗教は、どのように死を考えているのか」について述べられています。今このような本をお書きになった理由を教えてください。
橋爪大三郎さん(以下、橋爪):人間はみんな死ぬんです。しかし、死んだらどうなるのか、死ぬということがどういうことかわかっている人はいない。死んでみるまでわかりません。ということは、生きていることを本当にはわかっていない、ということです。それではせっかく生きているのにもったいない。
昔は年をとって自分の家で死んだり、兄弟姉妹が病気や戦争で死んだり、女性は出産で死ぬこともありました。家族が死ぬことは決してめずらしいことではなく、死は身近に存在していました。いまの日本の社会は平和で、寿命も長くなりました。核家族で家族の人数も少なく、死ぬときは病院で死ぬことが多いので、子どもは人が死ぬところを見ることがほとんどありません。
そして、死に本当に直面するのは自分が死ぬときだけ、という世の中になりました。つまり、自分が死ぬ瞬間まで死のことを考えなくていいわけです。平和で豊かになったから死を考えなくて済むようになった、それ自体はいいことですが、生き死にについて考える機会がないから考えないままでいい、というのはいけません。
これまで人類に大きな影響を与えた宗教は、キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、儒教、仏教の5つです。これまでたくさんの人が死んだらどうなるのか、を考えてきましたが、その中で死について一番考えてきたのは、こうした宗教をつくり、信仰をもって生きてきた人たちです。その人たちは長い間、一般の人に代わって、人間の生き死にについて考え切ってきました。その考え方には大事な生き方が詰まっています。
死について考えるならまず宗教を知るべきです。そうすれば人生について、世界について、死について、自分で一から考えずに済みます。いままで蓄積されてきた考え方は選りどり見どりですし、参考にして活用しなければ本当にもったいない。生きていることを死から照らし直してみましょう。そして本書の目的は、宗教についてもの知りになることではなく、自分で納得できる考え方をひとつ選び取ることにあります。
科学や哲学にはできないこと
――私個人(聞き手)はもし「生や死を考える」とするとしたら、宗教よりも、科学や哲学からアプローチしようと考えます。本書ではなぜ宗教を焦点にされたのでしょうか。
橋爪:科学と哲学も大事です。科学は、世界の真実はひとつであり、それを人類全体で追求していく、という考え方です。たくさんの人がいれば、これが真実だ、あれが真実だ、とそれぞれ異なる意見が出てきます。その意見とは、ある人が真実について考えたこと、つまり「仮説」です。そして、どの仮説が正しいか、ということは実験、検証した結果わかることです。この仮説、検証、実験のプロセスは「経験できる出来事」しか扱うことができません。しかし人間は「自分自身の死を決して経験できない」ので、死を考えることは科学が扱える範囲を超えています。どんなに科学が進歩しても、科学によって死を考えることはできません。
哲学は、経験できることだけではなく、経験できないことも含めて、人間が考える極限まで考えて、議論して正しいことを見つけていきましょう、という学問です。しかし実験や検証をすることができません。
死の問題に答えてくれない、ということは「自分がなぜここにいるか」という問いに答えてくれない、ということです。科学ではその問いに考える材料が足りないし、哲学は3分の1くらいしかヒントをくれません。宗教は、科学や哲学よりいくらかましで、前半の半分くらいを考える材料は提供してくれますが、その先の後半は自分自身で考えなければなりません。
コーランにも聖書にも、人間や人生、世界について「こう考えなさい」ということは書いてあります。しかし「あなたがどうすればいいのか」ということまでは書いていない。宗教とは「誰かの答案のまる写し」ではなく、そこから先は自分で考えるという態度です。DIYのように材料があって、ある程度は組み立て方がわかって、その先は自分の頭でじっくり考えれば自分の人生が自分のものになるんです。
宗教を軽視してきた日本社会
――宗教が中東紛争の原因になったり、日本においては過去にカルト教団による、社会に大きな衝撃を与えた事件もあったりしました。また、経済状況やライフスタイルの変化によって、葬式や墓はなくなったり、縮小化や低コスト化が進んだりしています。このようなさまざまな原因によって、宗教への関心は薄れて、宗教離れが進んでいるのではないでしょうか。日本社会において宗教とは何か、改めて教えてください。
橋爪:いま、世界にはヨーロッパ・キリスト教文明、イスラム文明、ヒンドゥー文明、中国・儒教文明という四つの大きな文明があり、どれも宗教を土台にしています。さまざまな文化、言語、民族の人びとが集まると、社会階層も分化してより複雑な社会になっていきます。そうするとだんだん考え方の違いが出てきて、問題も起こる。それを乗り越えるために共通の価値観や目標を持ちながら、切磋琢磨して経済や文化、科学技術を発展させてきました。
宗教は、死のことばかりではなく人間のこと、社会のこと、この世界のあらゆることを考えるもので、人間の社会に大きな影響を与えて養分をくれるものです。
しかし、日本はあまり宗教に関心をもたない珍しい社会です。日本では一貫して宗教や宗教者は警戒されてきました。日本の社会や政府のしくみと宗教は、そもそも折り合いが悪い。平安、鎌倉、室町、江戸、明治時代……宗教に入り込む人がいると危険視して、一向一揆やキリシタンの弾圧のように排除してきました。このように宗教を危険視して社会から排除するようなことは、イスラム教世界やキリスト教世界、インドではあり得ないことです、宗教が社会の根幹なのですから。
ある民族がただ生きているだけでは文明は何も生まれません。日本社会は、中国からは儒教や律令制、仏教など、ヨーロッパからは科学技術や資本主義、民主主義など、自分たちでは生み出せなかった文明の産物をちゃっかり拝借して、明治日本以降、近代社会のふりをしてきました。自分の足で立って、自分の頭を使わないで「テストで隣の席の人の答案を丸写し」してきたようなものです。だから日本社会は年中おたおたしている。元をたどるとそれはきちんと文明の成果と付き合っていないからです。
戦後日本社会は、宗教よりも経済を選びました。商売をしたり、会社に行って仕事をしたり、宗教がなくてもお金を稼げればいい、とやってきた。ビジネスで業績や売上、出世、家族のことだけを考えていれば当面、心は充実します。経済やビジネスが宗教になってしまった。しかし、ビジネスは人生の価値や人の生き死にまでは考えてくれません。心の中は空っぽで、埋まり切らない余白がたくさんあるのではないでしょうか。
選択、偶然と必然、運命
――「相対主義は、ものわかりがよい。でも、問題を解決しない。(中略)どれかひとつを選択しなければならない。」と述べられています。相対的にキリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、儒教、仏教の五大宗教を俯瞰することと、特定の宗教をひとつ選択することの結果はどう異なるのでしょうか。
橋爪:先ほど述べたように、哲学にはさまざまな考え方があって、どの考え方が正しいのだろう、と思っても実験、検証ができません。誰が正しいかわからないわけです。そうすると、根拠もないのに「文句を言うな。俺が正しいんだ」という人が出てくる、それをイデオロギーといいます。
20世紀を通して暴れまわって、最後に壊れてしまったイデオロギーがマルクス主義です。羹に懲りて膾を吹く(あつものにこりてなますをふく)といいますが、世界中の人が反省したんです。イデオロギーなんてものが出てくるとろくなことがない、哲学は人間の生きているこの世界の出来事に結論を出すことができないんだから、唯一の真理なんてないことにしよう、イデオロギーなんてもの自体がなければ平和だ!と。
そして、どっちつかずの態度である相対主義が広まった。たとえば政治、経済、環境についてこういう考え方があります、ああいう考え方もあります、と。何か自分の意見を言うと、それはあなたの考えですね、それではあなたの意見は何ですか、と聞くと、それはこれから決めますから、と言う。相対主義ではどれが正しいのかわからないし、結論がない。結論がなくてどうやって物事を決めていくのか。
哲学の本質は「選択して正当化すること」です。だから、人生というのは、選択をして自分の人生だと引き受けて正当化することです。
たとえば結婚。あなたはなぜこの人と結婚しようと決めたのか。そう聞かれて、理由をすらすら言えるのはおかしいのではないでしょうか。婚活なんかでは外見や仕事、収入、性格を挙げたり、スペックなんていう言葉まで出てきたりする。それでは外見や仕事、収入が条件を満たしていたら相手はだれでもいいのでしょうか。
そうではありません。世界に一人しかいない、あなたがいいんです、あなたと一緒に生きていこうと思いました、それが正解でしょう。そうだとするとなぜこの人に決めたのですか?と聞かれたら理由ははっきり言えない、ということになる。あなたを記述しつくす方法はない、と。それがわかったときが、結婚しようと思う瞬間のはずなんです。それが選択です。
人間は偶然に出会いますがそれは必然です。自分で選んでいると思ってるうちは選択ではありません。選ぶことができない、これしかない、理屈を超えて、偶然が必然になる、人生はそういう構造をしている。
宗教も同じです。本書でも紹介する考え方の中から選りどり見どりに選べます、とは言っていますが、選んでいるうちは選択ではありません。それを体得するためにいくつかの宗教からまずひとつ選んでみよう。それは一見、相対主義に見えるかもしれませんが、選んでやってみたら答えは初めから決まっていたんだ、ということに気がつきます。
あなたは先ほど、本書の中で紹介されている考え方の中では、仏教やヒンドゥー教が気になると言っていましたが、それは裏返して言えば一神教には関心をもたなかった、ということ。それが、自分の中にもう答えがあった、ということなんです。理由ははっきりしないけれども、決めることで現実が開けていく、その選択の積み重ねが運命ということではないでしょうか。
“梵我一如によれば、人間は実は人間ではなく、ただの因果連関である”
――バラモン教、ヒンドゥー教、仏教のベースとなるインド文明の思考について説明されている中で、「人間は、自分を生き物だと思っているが、ほんとうは、ただの因果連関にすぎない(中略)人間はほんとうは、生き物ではない。のだとしても、生き物として生きており、自分を生き物だと思っている。そのため、生きるためにあくせくし、欲望にとらわれている。仏教の言い方では、煩悩である。本当は生き物ではないのに気の毒だ。」と記されています。
目の前のことで頭がいっぱいの現代人が、そこから抜け出すためにもっと大きな思考の枠組みを得るために、全体と自分をつなげて考えることで死というものの見方が変わるでしょうか。
橋爪:インドの人びとの考え方の基本である因果論(仏教では、因縁、縁起とも言う)にそのヒントがあります。これは原因があって結果がある、原因がなければ結果がない、という世の中の出来事を因果の連鎖でとらえる考え方です。
この因果論のロジックを徹底して、自分はなぜここにいるのかと考えてみると、自分がいる原因は「父親と母親がいて生まれた」ということになる。では、父親と母親はなぜいるのか、と考えるとよくわからなくなりますが、それでも徹底的に考えていく。すると、自分がここにいる原因は自分ではない、ということになる。自分が原因となって結果が生まれるのは、この先の自分の行動やたとえば老後のことで、その後死んでしまったら自分自身はなくなるかもしれませんが、その影響はどこまでも続いていきます。この世界のあらゆる出来事は、「このわたし」も含めて、この原因と結果の連鎖のネットワークの中で起こっている、と考えられます。
宇宙もこの因果関係の連鎖のネットワークで、人間も宇宙に他ならない(梵我一如)。だから人は死んだとしても、自分を構成している炭素や窒素や水素はまだ存在していて宇宙と一体化する。人間は生き物でもなく、自分が人間だと思っている、他人が自分を人間だと思っている、というだけで、それは根拠のない思い込みではないか。世界の実際の姿はそんなものを越えているのではないか。これは、人間は自分を生き物だと思っているが、たまたまある組み合わせになったときに生き物とか人間になる、ただの因果連関にすぎない、という実は恐ろしいことを言っています。
“輪廻するなら、人間は死ぬとまもなく、別な人間や動物に生まれ変わる”
――輪廻を日本人が信じなかった、輪廻という考え方が定着しなかったのはなぜでしょうか。
橋爪:インド人の場合は死んだら生まれ変わると空想します、それが輪廻です。仏教やヒンドゥー教を生み出したインド人の思考力は凄まじいものです。ふつうの人がパソコンだとしたらスパコン(スーパーコンピュータ)のレベルです。輪廻というのは、自分をはみ出した世界のメカニズムであり、それを体験することなんです。
日本人は生まれてから死ぬまでの間のことしか考えないし、死ぬと自分というものは終わってしまうと考える。死んだら幽霊や魂になって、他の人の記憶の中で生きていきますが、その他の人も死んでしまったら自分についてのメモリーも消えて、本当にいなくなってしまう。輪廻もしないし、世界に戻っても来ないという素朴な死生観なんです。
“死は、本人の行為をはみ出す、自然の出来事である”
――「死ぬ前に、周囲の誰かにはっきりと意思を示しておかなければならない。その意思どおりにことを進めるのは、死ぬ本人ではなく、ほかの誰かだ。そのことの進め方が、本人の意志どおりである保証は、どこにもない」、死は本人の行為をはみ出している、と述べられています。とくに日本では臓器移植、延命措置など「死」について、本人よりも家族の選択が優先されることがあります。
橋爪:医学は世界共通でルールやはっきりした規準があります。日本とは異なる文化の前提にたっている西洋医学と、日本の慣習をもとに考えるからねじれてしまいます。
以前は呼吸停止、心停止、瞳孔散大が医師による死亡診断の標準でしたが、人工呼吸器が使われるようになると、呼吸停止が死の要件に適さなくなりました。脳が機能を停止して、回復不可能であれば、臓器を移植する、その判断は医師が行いますが、それには規準が必要です。西欧諸国では、個人の身体は「神がその人に与えたもの」なので、この個人の支配下にある。本人が臓器提供を望めば、家族といえどもほかの人間はそこに介入することはできない、と考えます。
一方、日本では、本人の意思に対して家族は拒否権をもっているし、本人の意思が絶対ではありません。また、本人が意思しなくても、家族が同意すれば移植ができます。本人がいつどのように死ぬのかについて、本人の意思が最優先されるとは言い切れず、本人の身体(遺体)の処分に家族の意思が及ぶということです。脳死や臓器移植に限らず、日本では個人としての本人よりも家族の介入や発言力が大きい。
例えばがんになっても、日本では自分の身体のことなのに本人に知らせないで、配偶者や家族だけに知らせたり、家族に対して病状や今後の治療方針を説明したりします。アメリカでは、本人の病状を本人に知らせないで家族だけに知らせるというのは医者側のルール違反になります。本人の利益を守るために本人に告知すべきで、家族に対しては秘密にしなければなりません。子どもが成人したら、子どもの病気については親には言わないし、親の病気についても子どもには言ってはいけません。ましてやある人がいつ死ぬか、ということを家族が決めるなんてありえません。そのような個人の身体のことはその人自身のもの、という考え方の先に脳死や臓器移植、延命措置の問題があります。
どれかひとつの考え方を選択すること
――「宗教の、どれかひとつを選んで、死んだらどうなるか、考えてみる。ちょっとやってみる、をお勧めする。それは、運命の出会いかもしれない。」と、特定の信仰を持っていない人にどれかひとつの宗教を選択してみるように提案されていますが、ふつうの大人が今からひとつの宗教を選ぶことはできるのでしょうか。
橋爪:宗教を信じましょう、という本ではなく、宗教を踏み台にすると死を深く考えられますよ、という提案です。
人は、さまざまな選択を重ねて自分の人生をつくっています。進学、仕事、結婚・・・一人一人がひとつずつ選びながら子どもから大人になっていきます。自分の人生とは、自分の選択の積み重ねの結果でそれを引き受けることです。しかし、必要な選択をすべて自分でしているでしょうか。
人間はみなやむを得ず死にます。死は選択する余地なく、これからいつか必ずやってくるものです。それは自分の人生にとって何でしょうか。死を考えることができないなら生きることも考えられないし、人生にぽっかり穴が開いたままになってしまう。「夏休みの宿題」のように後回しにしないで、しっかり引き受けて考えないと自分の人生は完結しません。
長い人類の歴史の中でいままで死を人がどう考えてきたのか―それが、私が本書で紹介した一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)インドの宗教(バラモン教、ヒンドゥー教、仏教)、中国の宗教(儒教、道教)、日本の宗教や近代人の死の考え方、です。その中で「これがいい、この考え方が気に入った」とひとつ選んで生きてみる。どれかひとつを選択したふりをするだけでもいい。それでも病気にかかる前のワクチンみたいなもので、あなたの人生に十分プラスになるでしょう。(以上)

『死の講義』
橋爪大三郎 著
ダイヤモンド社 刊