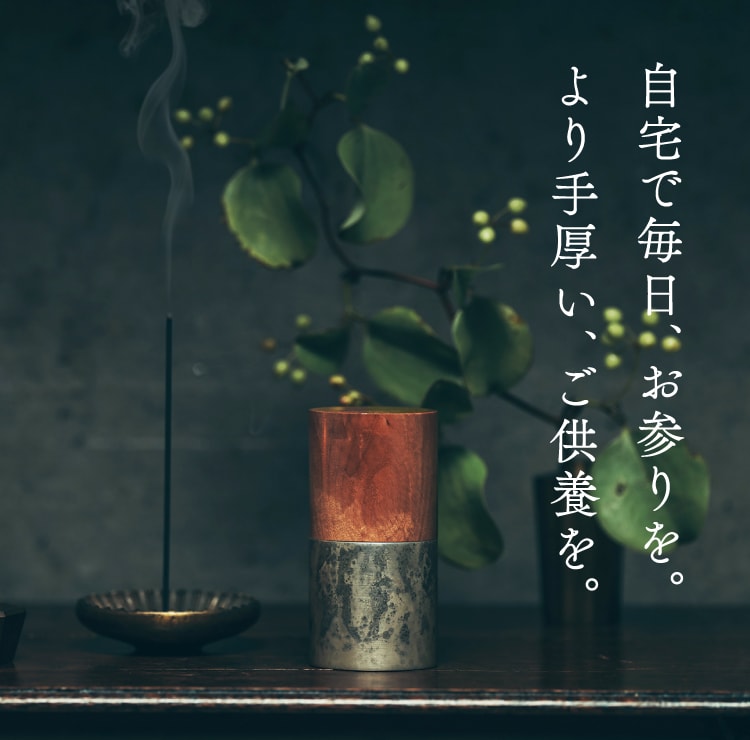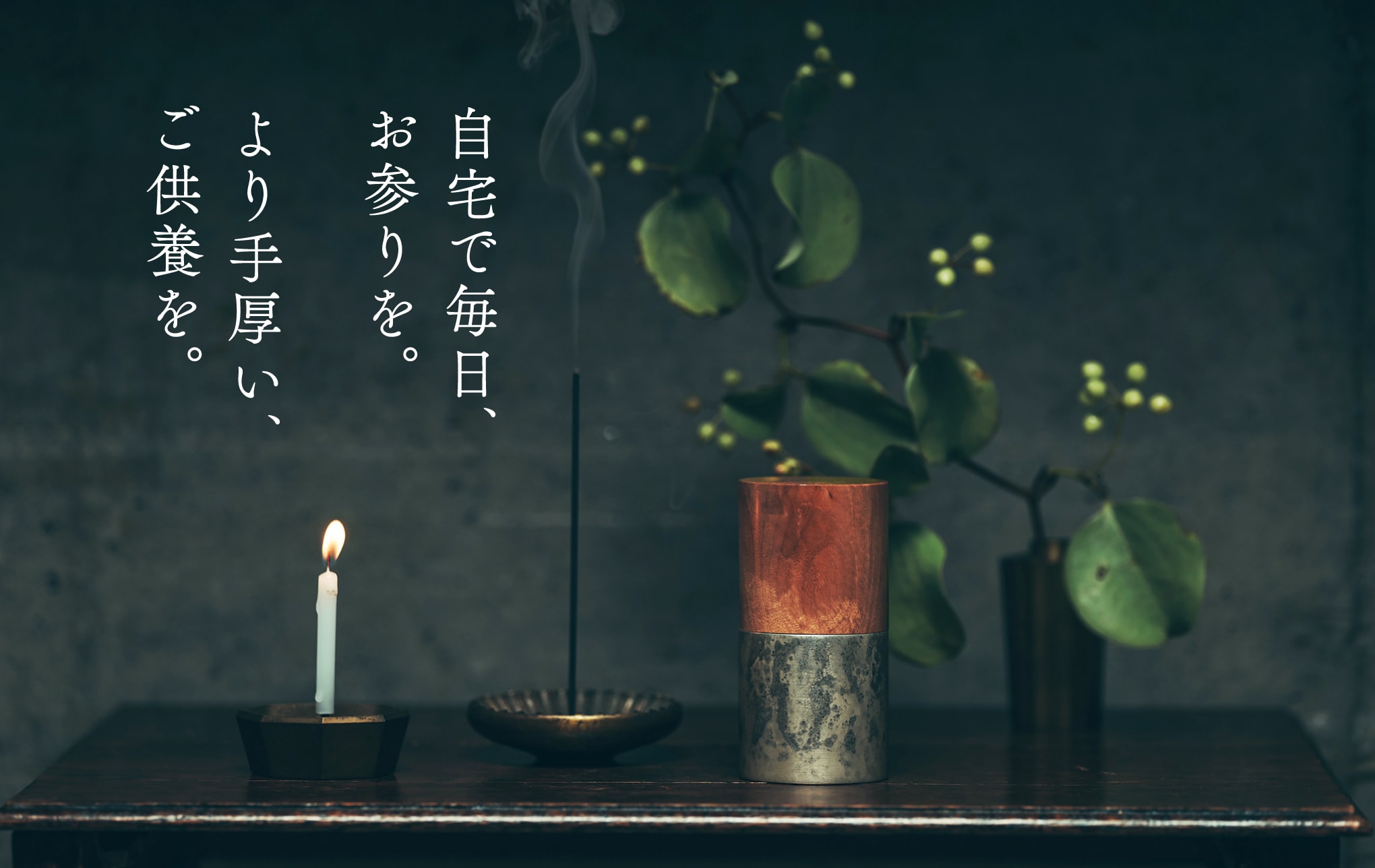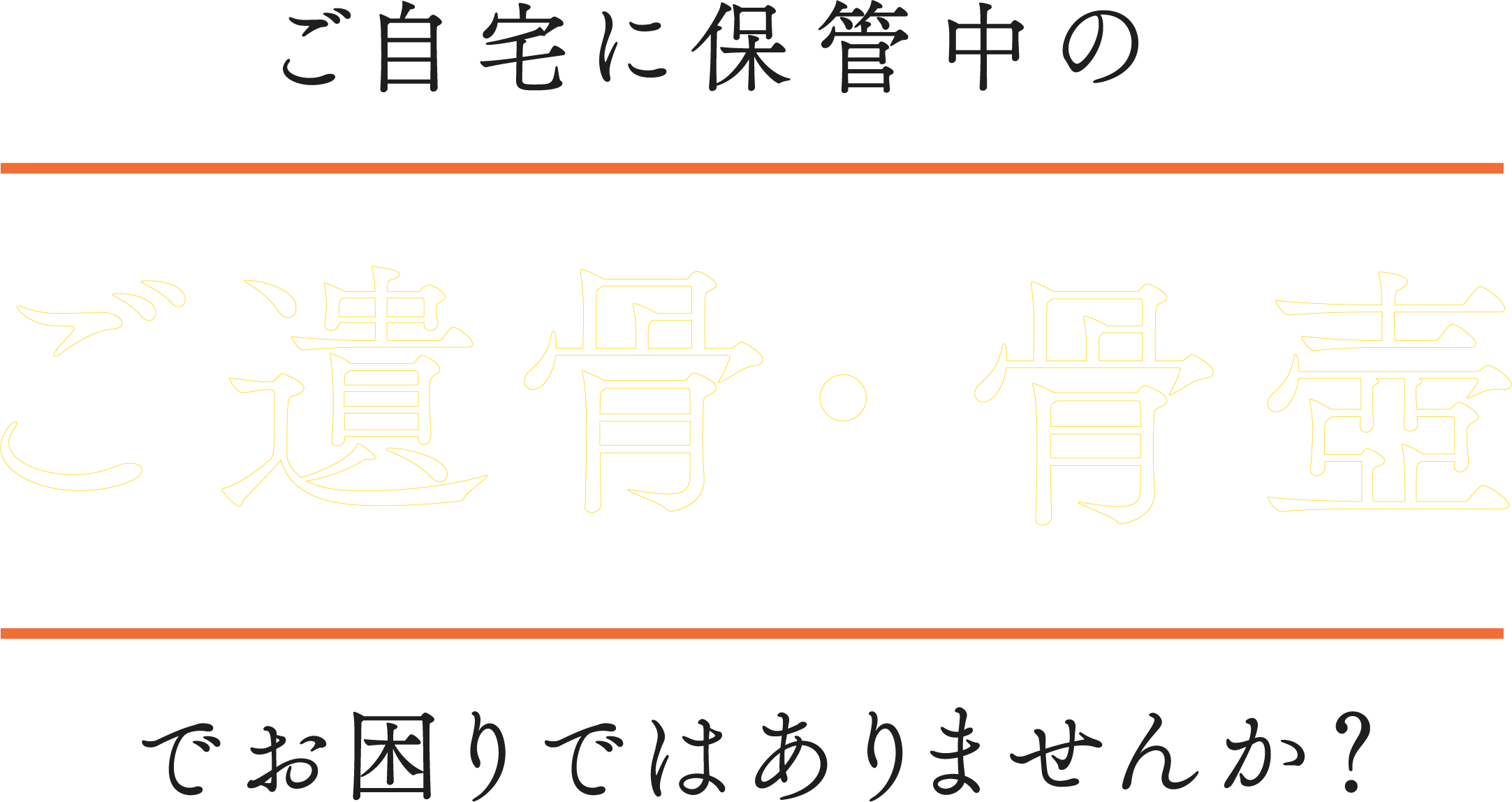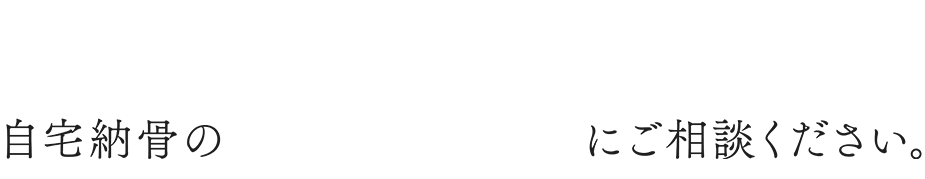弔問とは、訃報を聞いて故人の遺族を訪ねてお悔やみの言葉を伝えることです。自宅等を訪ねる以外にも通夜・葬儀に参列することも弔問と言います。訃報を受けてすぐに弔問する、通夜・葬儀に参列する、葬儀後に弔問する…いつどのタイミングで弔問するかは故人との関係性や葬儀の種類によって変わります。今回は弔問するタイミングと弔問前後の流れ、持ち物や服装についてご紹介します。弔問のタイミングに応じた服装や行動を知り、突然のお悔やみにも落ち着いて対応できるようにしましょう。
弔問はいつ誰がどのようにするのか?~タイミングや流れ、持ち物、服装
1. 訃報を受けた時の対応
遺族から訃報を受けたら、突然の連絡に動揺してしまうかもしれませんが、まずは以下のようなお悔やみの言葉を伝えましょう。
「お悔やみを申し上げます」
「ご愁傷さまです」
「突然のことで何と申し上げてよいものかわかりません。心からお悔やみ申し上げます。」
その際、次のようなことに留意をつけましょう。
- 「がんばって」等と無理に励ます必要はありません。
- 死亡の知らせを受けた側から死因や死の経緯等を聞かないようにします。
- 「重ね重ね」「度々」「くれぐれ」等不幸が重なることを連想する「忌み言葉」を使わないようにしましょう。
- 遺族は通夜や葬儀の準備で慌ただしくしているかもしれないので、簡潔にお悔やみの気持ちを伝えます。
- 通夜や葬儀の有無や、もし決まっているようであれば日程や会場を聞き、まだ決まっていないようであれば、後から知らせてもらうようにしましょう。
2. 弔問するタイミング
弔問するタイミングは大きく分けて、訃報を聞いてすぐに駆けつける、通夜や葬儀・告別式に参列する、家族葬の場合等葬儀後に弔問する、という3つがあります。そのタイミングで弔問するかは故人との関係性や葬儀の種類によって変わります。
2-1. 訃報を受けてすぐに
家族・親族は、亡くなって死亡の連絡を受けたら、できるだけすぐに駆けつけましょう。葬儀の準備や遺体のケア等のためにも人手が必要な場合もあります。
親族ではない親しい間柄の友人等は、通夜の前に弔問するのは基本的には控えた方がいいでしょう。ただし、故人と特に親しくしていた場合や遺族にぜひ顔を見に来てほしいなど要望があった場合は、事前に遺族へ確認した上で、亡くなった病院や遺体が戻ってきた自宅を訪ね、お別れを伝えるケースもあります。
2-2. 通夜や葬儀・告別式に参列する
通夜や葬儀には、家族や親族、友人、知人、仕事関係や近所の人等が参列します。家族葬ではなく一般葬であれば、上記のような家族や親族、特に親しい友人以外は遺族が対応する負担が増えてしまうので、弔問ではなく通夜または葬儀に参列するようにします。
近所の人が亡くなった場合は、通夜や葬儀の知らせを受けて、通夜や葬儀・告別式に参列するのが一般的です。ただし近所づきあいが深い場合や、近所の人が葬儀の準備や手伝いをする地域の場合は、通夜の前に弔問することもあります。
仕事関係の人が亡くなった場合は、個人としてではなく会社として対応します。まずは上司と連絡を取りその後の対応を相談しましょう。
知人・友人は、通夜または葬儀・告別式のいずれか、もしくは両方に参列します。家族葬の場合は、通夜・葬儀に参列しないので後日弔問することになります。
2-3. 葬儀後に弔問する
やむを得ぬ事情により通夜や葬儀・告別式に参列できない場合や家族葬の場合、葬儀が終わってから訃報を知った場合等は葬儀後に弔問するようにします。
葬儀後は、葬儀後3日以降から四十九日までの期間に弔問します。まず、遺族へ連絡し、伺ってもよいか尋ね、弔問の日時は遺族の意向に合わせて、もし断られた場合は無理を言わずに引き下がりましょう。弔問の際の服装は平服です。当日は玄関先で挨拶をし、促されたら家へ上がり線香をあげます。詳しくは次の「3. 弔問の流れ」をご覧ください。
3. 弔問の流れ
故人と特に親しい仲で訃報を受けてすぐに駆けつける場合や、葬儀が終わってから弔問する場合の流れについて、ご説明します。
3-1. 遺族へ確認
弔問する場合は、遺族に事前に以下のことを確認してから伺います。
- 弔問してもいいかどうか。
- 日時
- 弔問する場所(個人の自宅または遺体のある場所や実家等)
遺族の悲しみが大きいため弔問を受けられる状況ではない場合や、通夜や葬儀の準備を始めていること等から、弔問を断られた場合は無理を言わずにすぐに引き下がるようにしましょう。
3-2. 服装・持ち物
弔問は平服でするのが一般的です。それほど厳密な服装のマナーはありませんが、黒や紺、グレー、白等の地味な色合いのスーツやワンピース、ジャケット、シャツ等を着用し、派手なアクセサリーは身に着けない方がいいでしょう。
もし自分の都合で通夜や葬儀・告別式に参列できなかった場合は、香典を持参します。家族葬だった場合等の事情で後日弔問する場合は供物を用意するといいでしょう。高価過ぎない、故人が生前好きだったものや菓子、花等をお供えします。食べ物の場合は、日持ちするものが望ましいです。
香典について詳しくは以下の記事をご覧ください。
香典袋の選び方・書き方~表書きは宗派ごとに違う?連名の順番は?
3-3. 玄関先で挨拶
故人の自宅を訪問したら、玄関先でまず遺族に次のようなお悔やみの言葉を伝えます。
- 思いもかけないお知らせをいただきまして、駆けつけて参りました。突然のことで言葉もございません。心よりお悔やみ申し上げます。
- 会社でいつも○○様にお世話になっておりました△△でございます。この度は突然のご不幸、ご愁傷さまでございます。
3-4. 線香をあげる
遺族に勧められたら家に上がり、線香をあげましょう。
線香による焼香の手順は次の通りです。
- 祭壇や仏壇の手前まで進み出る、座布団に正座し、遺影に向けて一礼。
-
線香を手に持ってろうそくの炎に近づけ、線香に火をつける。

- 炎が出たら手であおぐか、線香を上から下にすっと下げて消す。息を吹きかけて消すのはNG。通夜や葬式・告別式に参列しない場合は、この時に香典やお供え物を渡します。
-
線香を香炉に立てて手を合わせる。

線香の本数や、線香を立てるか寝かせるかは次の通り、宗派によって異なりますが、必ずしもこの通りでなければいけないというわけではありません。
| 臨済宗・曹洞宗・日蓮宗 | 1本 | 中央へ立てる |
| 真言宗・天台宗 | 3本 | 上から見て逆三角形になるように立てる |
| 浄土宗 | 1~3本 | 中央へ寄せて立てる |
| 浄土真宗 | 1本 | 1本を二つに折り、2本同時に火をつけ、左側に火がついた方がくるように寝かせる |
3-5. 故人と対面する(訃報を受けてすぐに駆けつけた場合)
故人との対面は、「お顔を見てお別れをしてやってください」等、遺族から促された場合のみ可能です。「ありがとうございます。対面させていただきます。」と遺族にお礼を言い、対面するようにしましょう。悲しみが大きく、対面すると取り乱してしまいそうな場合は「お会いするのが辛すぎますので」等と丁寧に断れば失礼になりません。
故人と対面する流れは以下の通りです。
- 故人の枕元から少し下がった場所で正座して両手をついて一礼。
- 遺族が白布を外したら、両手を膝の上において対面する。
- 故人に一礼して合掌。
- 少し後ろへ下がり、遺族へ一礼。
- 遺族へ「穏やかなお顔ですね」等、悼む言葉をかけ、その場を離れ、長居をせずに引き上げるようにしましょう。
自宅を訪ねる以外にも通夜・葬儀に参列することも弔問と言います。通夜・葬儀への参列について、大まかな流れをご紹介します。詳しくはそれぞれの記事をご覧ください。
4. 通夜や葬儀・告別式に参列する
続いて通夜や葬儀・告別式に参列する際の流れについてご説明します。突然の訃報にも落ち着いて対応できるように、弔問の流れを確認しましょう。
4-1. 服装・持ち物
地域によって通夜は平服で参列する場合もありますが、一般的には通夜や葬儀・告別式は喪服で参列します。香典を袱紗に包んで持参し、数珠やハンカチを持っていきましょう。
通夜に参列するときの服装や持ち物、香典袋の書き方については、つぎのコラムでくわしくご説明します。遺族へ失礼のないようにマナーを確認しておきましょう。
通夜の参列のマナー 服装と持ちもの、焼香等
香典袋の選び方・書き方~表書きは宗派ごとに違う?連名の順番は?
4-2. 受付
受付ではハンドバッグや内ポケットから袱紗を取り出して並び、自分の順番がきたら袱紗から香典袋を取り出します。「この度はご愁傷さまです」等お悔やみの言葉と共に、受付の人に両手で香典袋を渡します。芳名帳に記帳して返礼品を受け取ったら、焼香の順番がくるまで式場の所定の椅子に座って待ちましょう。
通夜と葬儀・告別式の両方に参列する場合は、遺族が参列者を把握するためにも受付での記帳は両日行います。ただし香典は参列したどちらかで一度だけ渡します。翌日の葬儀で香典を持参する場合は「香典は葬儀にお持ちします」、すでに通夜で香典を渡している場合は「昨日も参列しました」等と受付で伝えるといいでしょう。
4-3. 焼香
式が始まり読経が終わったら、焼香が始まります。喪主、遺族、親族、一般参列者の順に焼香を行います。焼香の手順は以下のとおりです。
- 遺族へ一礼する
- 焼香代の前で遺影に一礼する
- 親指、人差し指、中指の3本で抹香をつかみ、目を閉じて額の高さまで掲げる
- 香炉に抹香を静かに落とす
- 合掌して一礼する
焼香の回数は宗派により異なり1~3回行いますが、参列者が多い場合は1回でも良いとされています。回数にこだわるよりもお悔やみの気持ちをこめて丁寧に焼香をしましょう。
4-4. 閉式
僧侶が退席し、喪主からの挨拶が終わると閉式となります。
通夜の場合は親族や故人と特に関係が深かった人に「通夜ぶるまい」が行われます。「通夜ぶるまい」は酒や軽い食事等、喪家から弔問客へ行われるもてなしで、故人と共にする最後の食事です。勧められたら遠慮せずに参加し、一口だけでも食事をするのがマナーです。
葬儀・告別式の場合は次の4-5. 出棺となります。
4-5. 出棺
葬儀や告別式で花入れの儀や釘打ちの儀等のお別れの儀式をしたら、棺を霊柩車に乗せます。一般参列者でもできる限り、霊柩車が火葬場へ出発するまで立ち会うのが望ましいです。霊柩車が出発する際は黙礼し、合掌して故人の冥福を祈りましょう。
4-6. 火葬
出棺した霊柩車は火葬場に向かいます。火葬場へは親族や近親者と特に親しくしていた人のみが向かいます。遺族から依頼された場合のみ同行しましょう。 火葬場では炉の前で読経、焼香を行い、棺を火葬炉に納めます。火葬中はお茶や菓子等を食べながら故人の思い出話をしつつ、1~2時間ほど静かに待機しましょう。火葬後は足から頭までの順に骨を拾う「収骨」を行い、骨壺に納めます。
4-7. 初七日法要、精進落とし
亡くなってから七日目に行う初七日法要、四十九日法要の忌明け後に行う精進落としですが、最近は葬儀当日に繰り上げて行われることが多いです。収骨が終わったら斎場へ戻り、遺骨を安置してから、遺族から僧侶や参列者に感謝の気持ちをこめてお酒や料理が振る舞われます。遺族も疲れていますので、あまり長居しないようにしましょう。
5. 弔問以外の弔意の表し方
近年は家族、親族のみで行う「家族葬」が増加しています。家族葬には、基本的に家族、親族以外の人は参列しません。家族葬の場合は、葬儀後の弔問も断られる可能性がありますが、静かに故人を見送りたいという遺族の意向を受け止めましょう。
また、結婚式や出産等の慶事を間近に控えている人は、遺族へ配慮して弔問を控えるのが一般的です。慶事が落ち着いてから伺ったり、弔電を送ったりします。弔問する場合も、話題選びは慎重にしましょう。
病気や高齢であることから、弔問自体ができない場合もあります。どうしてもお悔やみの気持ちを伝えたい場合は、香典や供物を送ることを検討してみましょう。