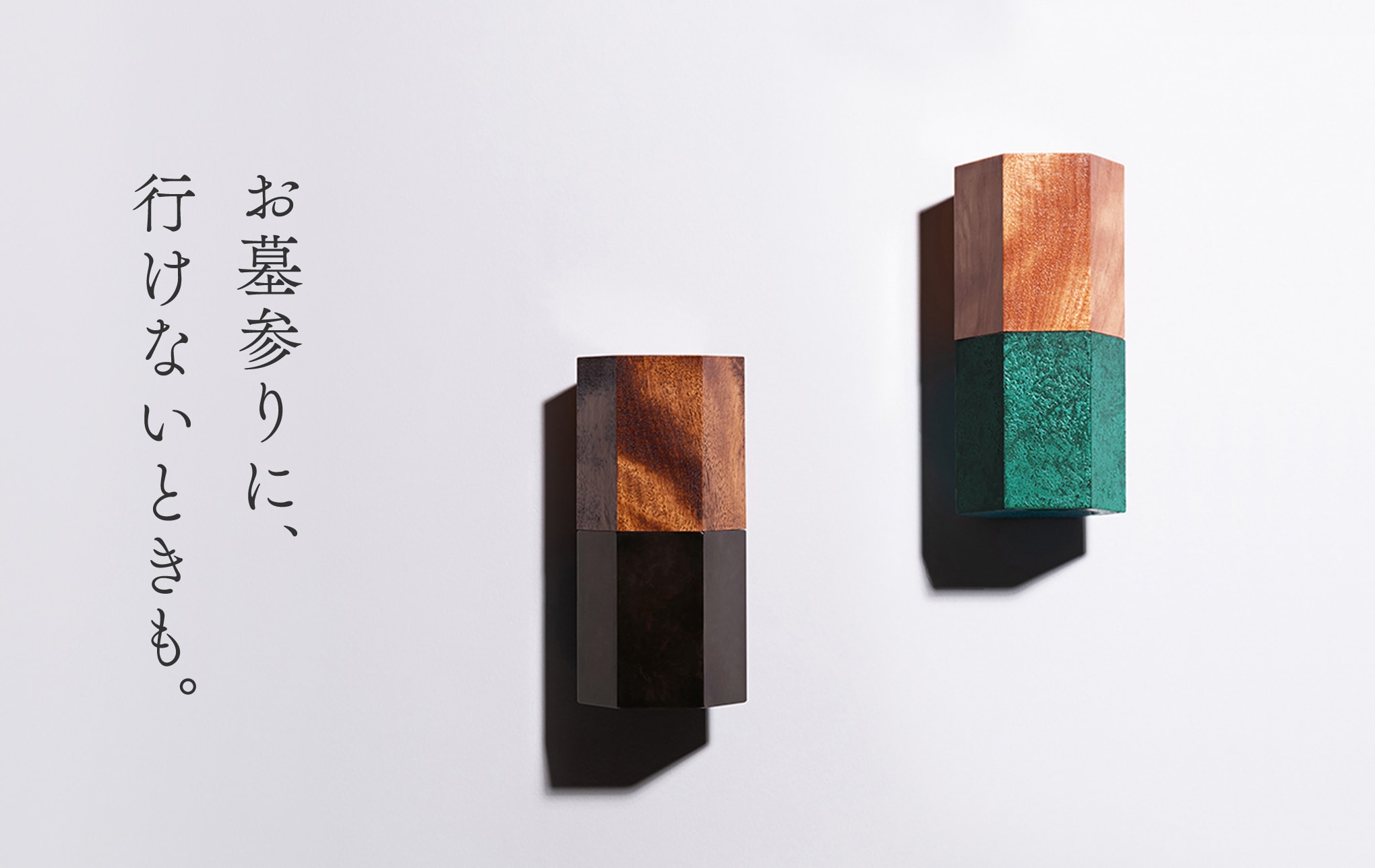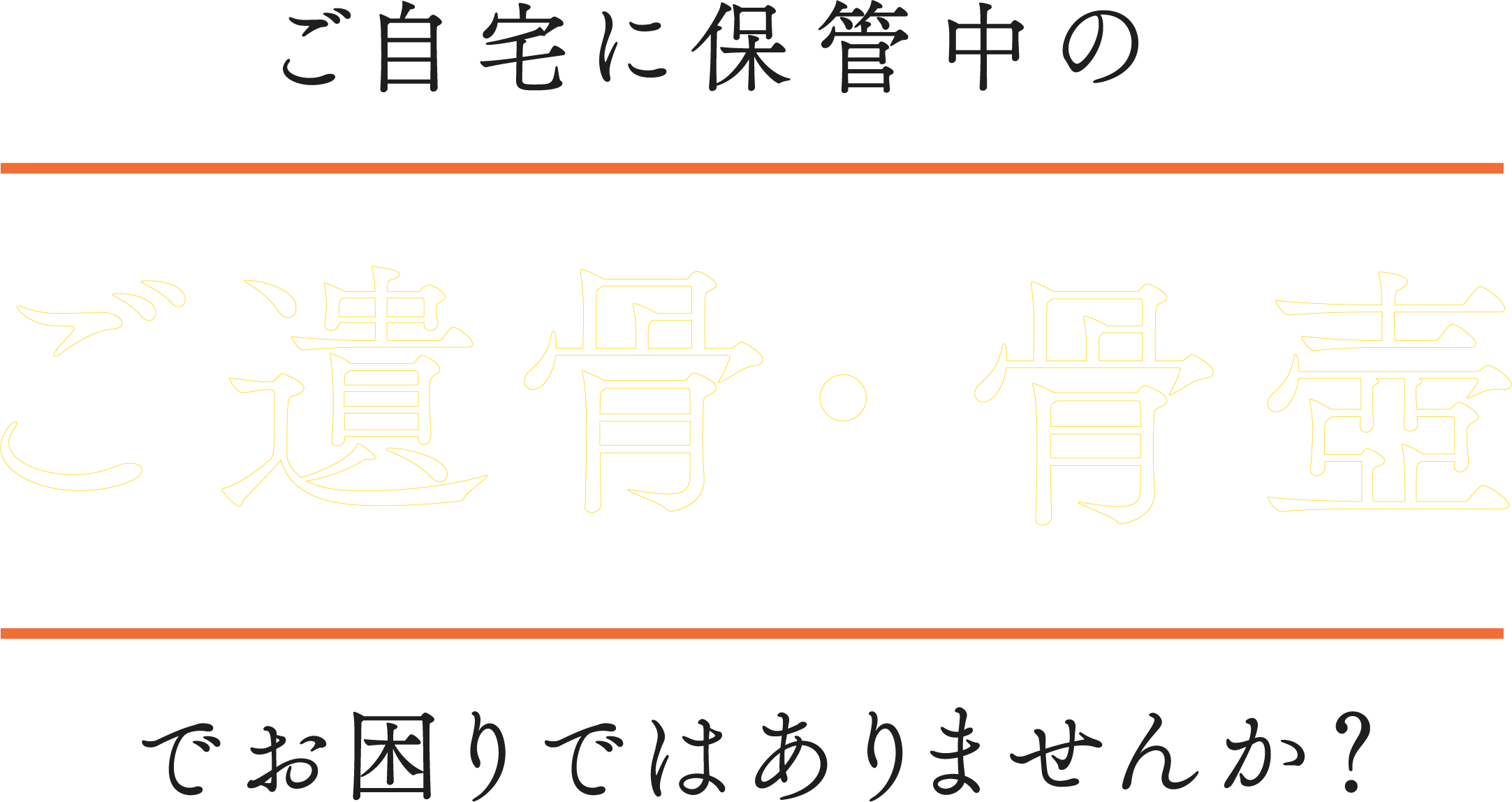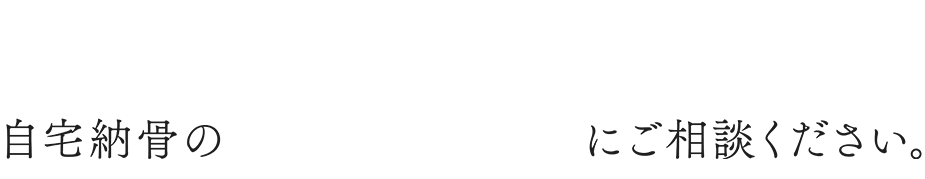今、日本を始め先進国で、宗教が捨てられている。しかもコロナウイルスが世界的なその傾向に追い打ちをかけている。―そう語るのは宗教学者の島田裕巳(しまだ・ひろみ)さんだ。
今回新型ウイルスが現れても宗教の出る幕はなかった。宗教施設に人が集まることはむしろ感染リスクを高めてしまったし、人々は信仰にすがるのではなく、感染拡大のデータ予測や具体的な予防方法を求めた。
平和で豊かな日本の社会では、老後や寿命は飽きるほど長くなった。生きているだけでお金はかかるから、死ぬまでのスケジュールを逆算しながら、何とか現実の生活をやり過ごさなくてはならない。誰が生きているのか、死んでいるのかもだんだんはっきりしなくなってくる。「死」が遠くなった時代の宗教、生き死に、人生とは?
『捨てられる宗教 葬式・戒名・墓を捨てた日本人の末路』(SB新書)を9月5日に上梓した島田裕巳(しまだ・ひろみ)さんに話を聞いた。(インタビュー日2021年1月12日、聞き手:シード・プランニング 鈴木皓子、長野光 構成:SOBANI編集部 添田愛沙)
本記事はこちらの動画インタビューのダイジェスト記事になります。動画もぜひご覧ください。

プロフィール
島田裕巳(しまだ・ひろみ)
作家。宗教学者。東京女子大学非常勤講師。1953年東京生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を歴任。学生時代に宗教学者の柳川啓一に師事し、とくに通過儀礼(イニシエーション)の観点から宗教現象を分析することに関心をもつ。大学在学中にヤマギシ会の運動に参加し、大学院に進学した後も、緑のふるさと運動にかかわる。大学院では、コミューン運動の研究を行い、医療と宗教との関係についても関心をもつ。日本女子大学では宗教学を教える。 主な著書に、『創価学会』(新潮新書)、『日本の10大新宗教』、『葬式は、要らない』、『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』(幻冬舎新書)などがある。とくに『葬式は、要らない』は30万部のベストセラーになる。生まれ順による相性について解説した『相性が悪い!』(新潮選書)や『プア充』(早川書房)、『0葬』(集英社)などは、大きな話題になるとともに、タイトルがそのまま流行語になった。本書は、世界と日本の宗教界が直面する危機を明らかにした『宗教消滅 資本主義は宗教と心中する』(SB新書)の続編に当たる。(このプロフィールは本書籍が刊行された時点のものです)
信者数のピークはバブル期、1989年
――「宗教が不要となった社会で今、何が起こっているのか。誰もが逃れられない生き死にの問題とどのように向き合っていけばいいのか。新型コロナウイルスによって突きつけられた問題の深層を解き明かしていく」と述べられています。今、このような内容の本をお書きになろうと思った理由を教えてください。
島田裕巳さん(以下、島田):2016年に同じSB新書から『宗教消滅 資本主義は宗教と心中する』という本を出しました。
宗教団体の信者数はバブルの時代がもっとも多く、1989年の平成の始まりの時点が日本の宗教人口のピークでした。しかしその後の平成30年間を振り返ってみると、仏教系で2300万人、神道系で1600万人と、各宗教団体の信者が大幅に減少している事実に気がつきました。それだけ多くの信者がわずか30年の間に減ってしまうなんてことは、日本の歴史の中で今までなかったのではないか。
世界の先進国で減り続ける信者
しかも信者数を減らしているのは日本だけの話ではなく、先進国共通の現象です。とくにカトリックは深刻で、西ヨーロッパでは、日曜日のミサに参列する信者の数が激減するなど、教会離れが著しく進んでいます。この現代社会の中で宗教という、おそらくは人類が誕生してからずっと存在したものが要らなくなってきている、これは非常に大ごとではないか。しかも今回の新型コロナウイルスによって、下手をしたらトドメを刺されてしまうような状況に至っているのではないか、それがこの本を書いた一番大きな動機です。
「死生観A」と「死生観B」
――平均寿命が長くなることによって、いつ死ぬか分からない時代の「死生観A」から、90歳くらいまで生きることを前提にスケジュール化された人生を生きる時代の「死生観B」へ死生観の転換がおきた。天国の存在を強く打ち出すなど「死生観A」を基盤としてきた宗教は「死生観B」の時代になったことで不要になっている、と述べられています。宗教はこのまま必要とされなくなるのでしょうか。
島田:昔は、病気にかかっても有効な治療法がなかったし、重い病気になれば確実に死に至りました。地震や災害で飢饉になったり、伝染病も蔓延したりして、平均寿命も短かった。還暦(満60歳)が祝いの対象とされてきたのも、それが一つの長寿の目安だったからです。
みないつまで生きられるかわからないし、いつ死ぬかわからなかった。現世の生活は苦しいもので、生きていても困難が多く幸福でないからこそ、信仰生活をまっとうして死後の世界に期待したい。極楽浄土に生まれ変わったり、天国を目指したり、よりよい来世に生まれ変わりたい、という願望が生まれました。これが「死生観A」です。
現在は、日本を含む先進国では平均寿命が延びて80歳を超えています。人生の終わりを90歳に想定して、そこから「逆算」してどう生きるかを考える。つまり「死」までがスケジュール化されている。これが「死生観B」。現代人はむしろ長すぎる老後や長い寿命を持て余して、戸惑いを覚えるほどになっています。いつ死ぬかわからない「死生観A」に立って考えることはもうできなくなってしまった。このように死生観が根本的に変わってきてしまうと、昔の死生観の上に作り上げられている宗教は必要とされなくなります。
かつてそこにあった、死のリアリティ
昔は、家族は自宅で亡くなったし、葬式も村単位で、戦後になると勤務先の企業が取り仕切ったりして、葬式に参列する機会も今より多かった。しかし今は、実際に亡くなってる人はたくさんいるのですが、自分の周りで死ぬ人があまりいないし、病院や施設で亡くなるので、日常生活の中で「人の死」に接することが少ない。
とくに若い人にとっては「自分は死なない」とまでは思っていないかもしれませんが、「死」がものすごく遠い出来事になっていて、リアリティがないのではないか。これは現代社会に特有の現象です。
現世の暮らしがとても豊かで安定したものになっているので、死は人生の最後に一応訪れることになってはいるが、それほど重要なものではなくなっている。すると「死んだ後に来世に生まれ変わりたい」という希望は浮かんでこないし、「死んだら地獄に落とされるのではないか」と恐れる人も、昔に比べるとはるかに減ってる気がします。死を身近に感じていた時代とは、死に対する感覚はずいぶん変わってきているのではないでしょうか。
宗教団体も超高齢化
――先進国では宗教が衰退し、日本でも既成宗教、新宗教ともに信者数を減らしているわけですが、宗教団体側では時代に即した存在になろうとする動きはないのでしょうか。
島田:かなり危機は感じていると思いますが、正直なところ、どうしていいかわからないのでしょう。
現在、各宗教団体がやっているのは、今いる信者を何とか減らさないようにすることです。しかし、やはり信者も高齢になると活動しなくなるし、まして信者が亡くなれば信者自体がいなくなってしまう。若い人たちを集めようと思っても、宗教を受け入れてくれる人や求めている人が一体どこにいるのか、という問題があります。若い人たちにとって宗教、特に宗教教団というものが意味のあるものになり得ていない。
この社会の中でどのような宗教に期待が集まるのか、と考えるととても難しい。私もどのように考えればいいか、と聞かれると非常に困るところがありますが、根本的な考え方を変えないといけないのではないでしょうか。
宗教台頭の要件は「経済成長」と「都市化」
――かつて新宗教がいくつか起こったように、現代において新しい宗教が起こる動きはあるのでしょうか。
島田:どんなときに新宗教が起こったり、宗教が信者を集めたりするかというと、経済発展が続いていて、地方から都市に多くの人たちが集まってくる状況が不可欠です。日本でも戦後の高度経済成長の時代に創価学会や立正佼成会などの新宗教が台頭しました。
地方の農村から若いときに都市に働きに出てくると、最初は賃金も安いし、雇用も安定しない。地方の村にあった人間関係は失ってしまったが、都会ではまだ新しい人間関係のネットワークもなく孤独である。しかし、宗教や信仰を通して、貧しく孤独な生活から脱して仲間のいる豊かな生活を得ることができるかもしれないし、社会の経済発展とともに、自分には明るい未来があると想像することができる。
経済が安定成長、低成長になると新宗教の拡大は止まる
中南米では今、従来のカトリックの信者が減って、プロテスタントの福音派が伸びています。おそらくこれも都市に出てくる人たちが多くなって、かつて日本の新宗教に求められたのと同じようなことが、プロテスタントの福音派に期待されているのではないか。これは従来の宗教のように来世に期待するのではなく、現世の現実の社会の中でいかに幸福に生きるか「現世利益の獲得」が重要になっていることの表れです。
宗教や信仰には、将来に対する期待が必要です。経済成長が続いている時代には、この社会で頑張って生きていけば必ず幸福になれる、という希望があった。しかし、この経済の発展が新宗教、あるいは新宗教的なものが拡大していく根底にあるとすると、日本のようにすでにもう経済が成長しきって、安定成長、低成長になっている国では新宗教が拡大する余地はすでになくなっているといえます。
アメリカの社会不安と宗教とトランプ
――昨年アメリカで大統領選挙がありました。アメリカでは福音派のクリスチャンにはトランプ支持者が多く、トランプは「神の申し子だ」と唱える人々の存在もメディアで取り上げられています。このような一部の熱狂的トランプ支持者は、支持というよりも盲目的に信仰しているようにさえ見えます。宗教が衰退すると、人々の中にある何かを信じたい、不安を癒したい、といった宗教的願望のようなものはどこへ向かうのでしょうか。
島田:アメリカの平均寿命は、2014年は78.84歳、2015年は78.69歳、2016年と2017年は78.54歳、と実は数年前から短くなっています。世界の国の中で見ても、アメリカの平均寿命は40位台に落ち込んでいます。
その原因として、薬物の過剰摂取や自殺、アルコール関連の疾患など社会的不平等と経済困難のために、生産年齢(25歳~64歳)のアメリカ人の死亡率が高まっているからだと言われています。アメリカ社会の秩序はかなり崩れてきていて、社会的な困難が高まっているのでしょう。そしてアメリカという国は果たして先進国といえるのかどうか、という疑問さえ出てくる。また、トランプ支持者である共和党の地盤になっている地域の信仰率が、他の地域に比べてとくに高いことも、そのような経済的、社会的な格差などの背景が関係しているかもしれません。
アメリカの平均寿命がこれからも短くなっていくと、いつ死ぬかわからない、いつまで生きられるかわからないので、先ほどお話しした死生観Aに戻っていく可能性もある。そうなると宗教の力が再び復活してくることもありえます。今後注視していく必要があるでしょう。
「死」は人生において重要な出来事でなくなる
――「今の時点で「私」が死んでいないことを、いったいどれだけの人が知っているのだろうか」「それは、私たちが知る他者についても言える。私の知り合いのうち、いったいどれだけの人が生存しているのだろうか」と述べられています。近年は「喪中はがき」で死を知らせたり、死を知ったりするということも少なくなってきました。死の知らせ方は今後どうなっていくとお考えですか。
島田:現代のように寿命が長くなると、まだ生きているうちから社会的な活動や人との関わりが少なくなって、まして施設に入ってしまえば音信も途絶えて、その人間が生きているかどうか知る人は少なくなる。死んだとしても、以前のように一般葬で葬式に呼ばれれば、死んだ事実はわかりますが、最近のように家族葬であれば、誰かから知らされなければわかりません。高齢で亡くなった場合には知らせを受ける人も高齢だし、もしかしたら相手も亡くなってるかもしれないので知らせる必要がない。死んだことを知らせる、知らせないというよりも、「知らせることができない」傾向が強まっていくでしょう。
「死」というものが、もう人生において決定的に重要な出来事ではなくなって、誰も知らなくてもそれほど構うことではなくなる。僕はある意味でこれは「孤独死」だと思う。一人で死ぬ、という意味ではなくて「死んだことを知らない」という意味での「孤独死」が、これからの基本になっていくのではないでしょうか。
しぶとい「遺骨」
――日本は世界一の火葬大国です。散骨、樹木葬など葬送の方法はさまざまですが、火葬すると遺骨は最後に必ず残ります。遺骨を本人の代替物と感じたり、納骨をしないと成仏しないのではないかと考えたりする人もいます。
島田:大昔から、遺骨が残っているとそれ自体が信仰対象になるというのはありました。遺骨を大切にするという習慣は、一般に火葬が普及してからのことです。土葬では遺骨が残らないので、遺骨自体に誰も関心を持ちませんでした。火葬することによって骨が残ってしまうから、その骨に対して何か特別な気持ちが沸いてくるわけです。逆に言えば、骨がなければみんなあまり気にしないと思う。
意外とこの「骨」というのがしぶといというか、扱いにくくなっている。日本の火葬場の技術は、立派にきれいに遺骨が残るように焼く、という方向でずっと来ているので、かえって面倒な方向に来てるなあ、と僕なんかは思います。
死んだら何になる?
――お墓を持たない人も増えてきています。後には何も残らないという前提で考えた方がいいのでしょうか。
島田:柳田国男は、先祖をその家の繁栄の基礎を作り上げた存在とし、人は亡くなってから「先祖になる」ととらえました。しかし少子化が進み、兄弟姉妹の数も減り、企業勤めが増えた現在では、繁栄させて守っていく家もないので「先祖になる」ことは目標になりません。
最近聞いたのは、死んだら「勇者」になる「勇者の墓」を作ろうというアイデアです(※)。死んで別の何かになる、という目標を立てるとか、死んだら何かに生まれ変わる、と宣言しておいて、もしそういう人が現れたら私だと思ってください、という終わり方も今後は出てくるかもしれません。
※「ドラゴンクエスト」シリーズの生みの親である堀井雄二さんが作りたいと話している「勇者の墓」のこと。「墓を作ってもしょうがない」という人のために、「お墓+データベース」に勇者として、その人が生きてきた記憶をしまっておける。訪れた人にデータを見せることで「この人はこういう人生を送ったんだ」と知ってもらう、というアイデア(2021年1月11日、AERA.dot)
宗教団体に置き換わるのはAIか
――アメリカの知識人の中には宗教がグーグル(Google)やアップル(Apple)といったテクノロジー企業に変わった、という意見があります。実際にGoogle検索に知りたいことを打ち込めば何でも回答が返ってきます。テクノロジー企業に宗教的な意味づけがされていくことについてお考えをお聞かせください。
島田:先日ちょうど『人類が生み出した全知全能の存在は神になりうるか?』という本を出しました。我々の社会では、宗教よりAIに頼った方が解決できることが増えてきています。AI(人工知能)の進化によって、今までの人間の知性とは異なる、新しい知性が生まれつつある。AIは人間の考え方とは全く違う発想をする存在です。そのような存在を人間が作って、この社会に生まれ出てきたことの意味は非常に大きいと感じています。
粘着質な高齢者にならない方法
――100歳近くまで長い老後を生きて孤独な死を迎えることになる現代人が、老後を飽きずに生きる戦略として、学び続けて世界を分析的に見て理解すること、と述べられています。長い老後を過ごしていく戦略や心構えについてお聞かせください。
島田:人間にとって好奇心はとても大切です。若さを保つ上でも、好奇心を持っていないとかなり苦しいでしょう。年を取ってくると、とかく今の世の中の若い人たちに対して苦言を呈したり、今の政治が悪いと批判ばかりしたり、ネトウヨになってしまったり、そういう方向に行きがちなんです。これが僕は一番危ないと思う。一度そういう方向に行ってしまうと戻って来ることができない。だから、世の中を引いて見るような、我々はどうせもう死ぬんですから、くらいの姿勢でいいと思う。世の中を真っ正面から見るのではなく、横の方から眺めてみるような視点も必要ではないでしょうか。
原体験と宗教学者としての今後
――学生時代に宗教に関心を持って研究を始められたそうですね。
島田:子どもの頃、東京の杉並区の和田というところに住んでいたのですが、近所に立正佼成会の教団本部がありました。本部の大聖堂はインド風のピンク色の変わった建物なんですが、それがだんだん出来上がっていくのを見ながら小学校生活を送りました。小学5年生のときようやく大聖堂が完成すると、そこにたくさんの信者の方たちが集まって来た。その光景を目の当たりにして、これは一体何だろう?と思ったのが宗教に関心を向けた最初のきっかけです。学生時代は学生運動の時代でした。社会を変えていく運動全体に関心がありました。宗教もその一つで、学生運動の中で、精神的な運動みたいなものが「精神世界」という形で関心を持たれるようになっていました。その大きな流れが自分に影響したのかもしれません。
現在のように社会において宗教が力を失ってくると、じゃあ人間はどうやって生きていったらいいのか、が求められる。宗教学者としては、今後やはりそこに応えていかなければいけないと思っています。

『捨てられる宗教 葬式・戒名・墓を捨てた日本人の末路』SB新書
島田裕巳 著