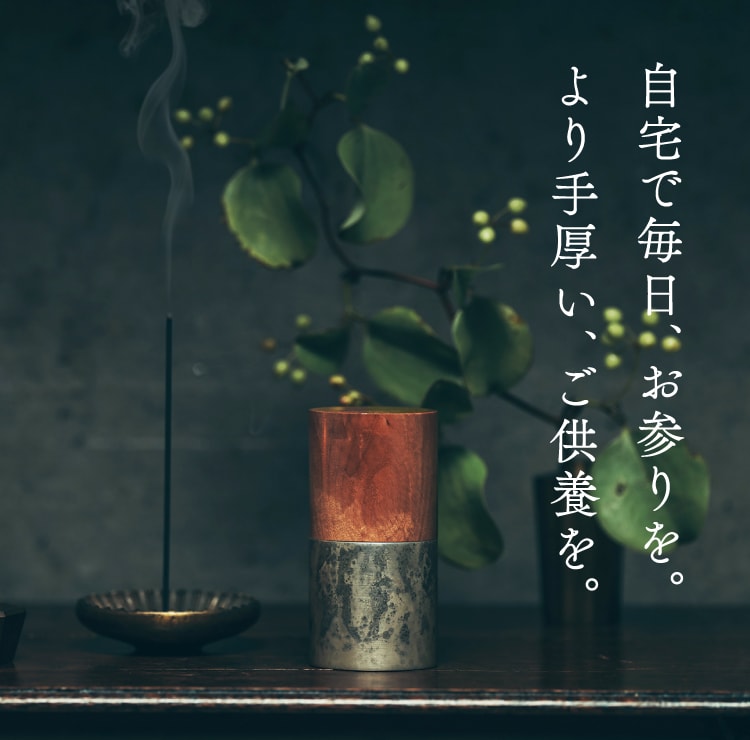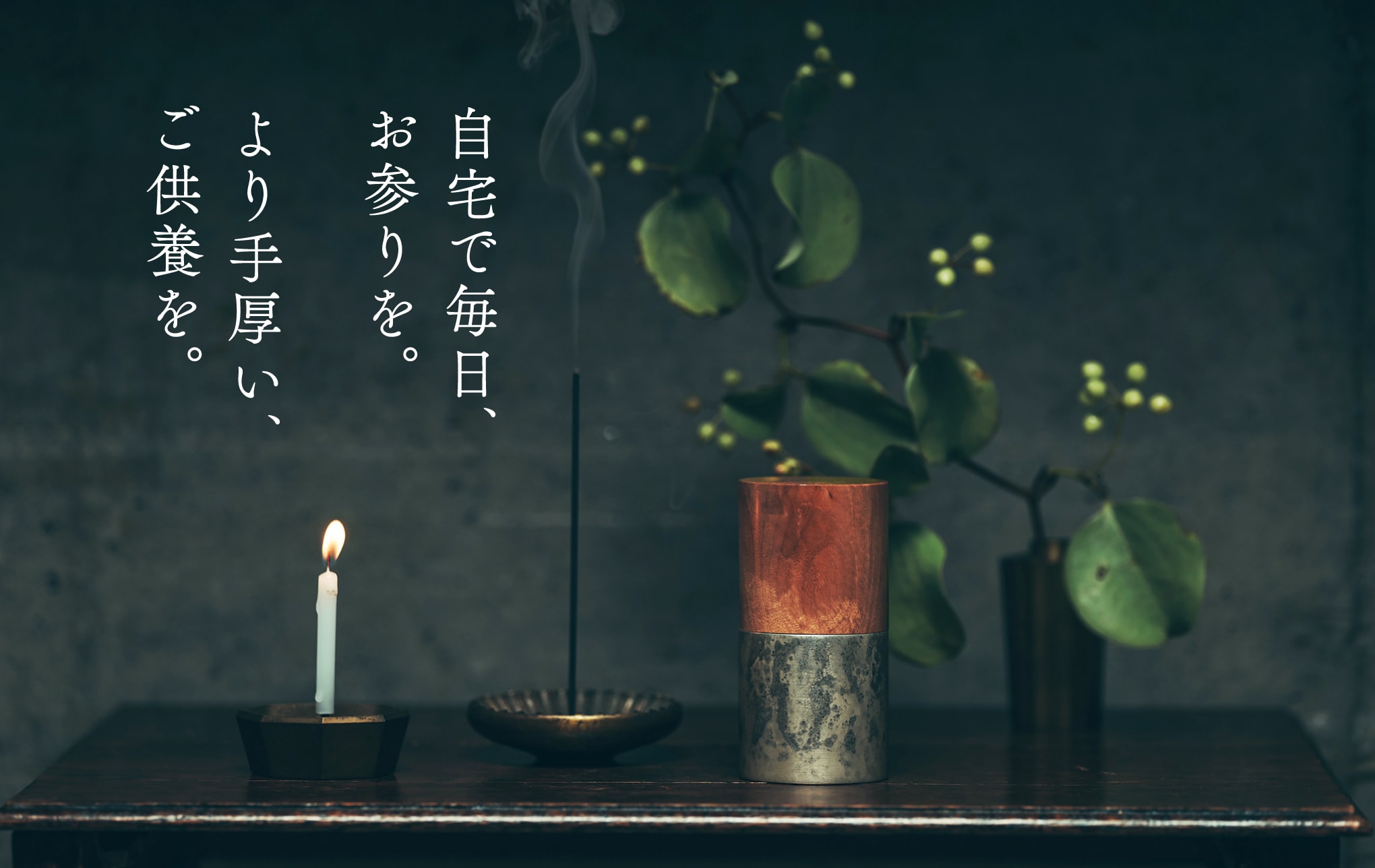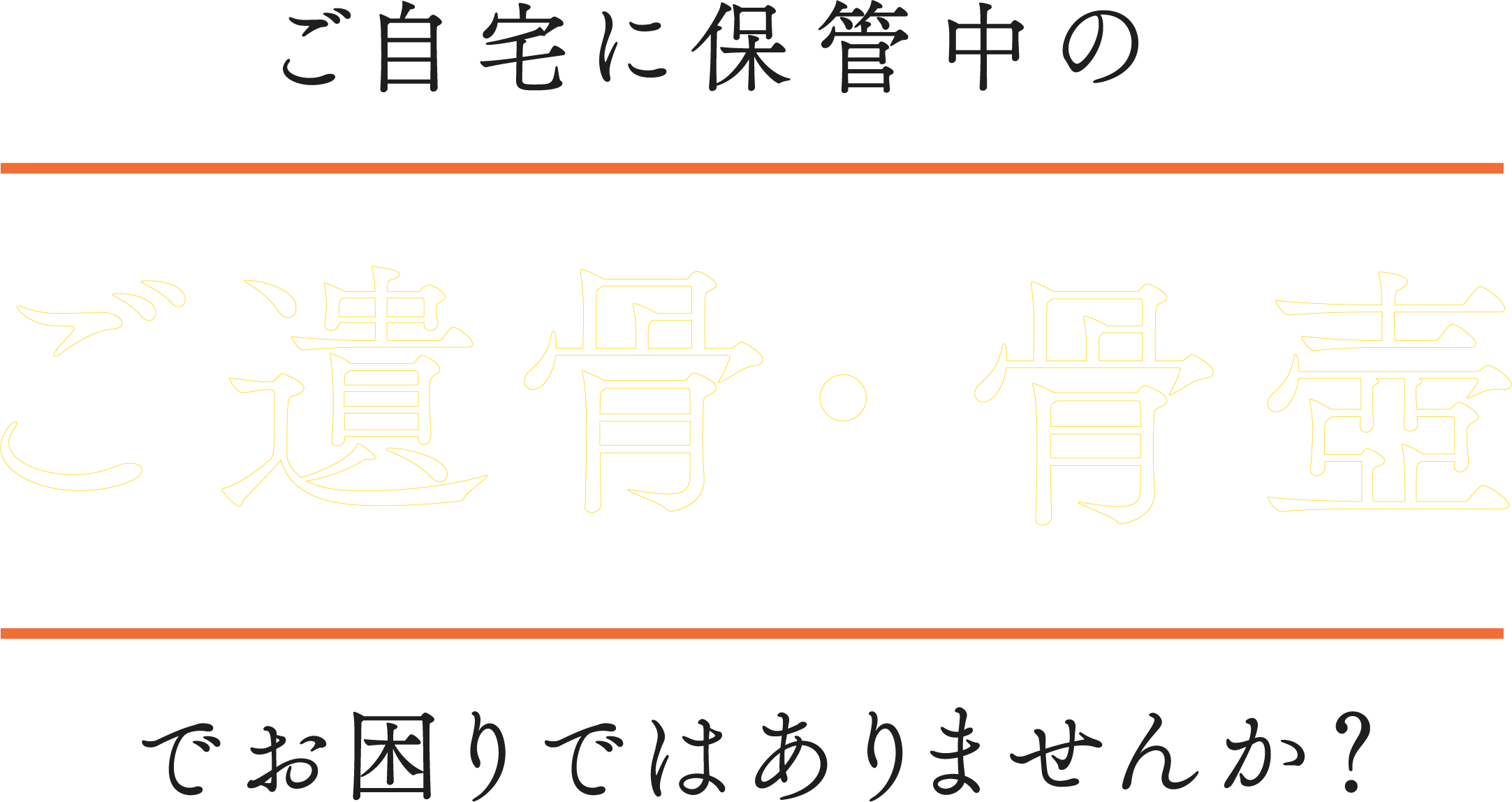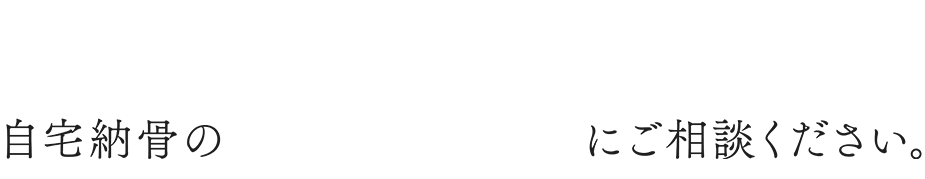近しい人を亡くし葬儀や供養を行うだけで精一杯。相続手続きなんて自分でやれそうもない。ネットでも専門家に依頼するように書かれている。お金がかかっても専門家に頼めば楽だし、安心かな・・・。そう考えませんか?実は私もそうでした。でも、ひょんなことから自分で相続手続きを全部やることになりました。簡単ではありませんでしたが、相続手続きを全部終えた時、専門家に頼んでいたら、きっと得られなかっただろう、大切なものをもらいました。今回は私の体験談とともに、自分で手続きする場合のコツや役に立つ情報をお届けします。
相続手続きを自分でやってみた!コツ・お役立ち情報満載の実録ドキュメント
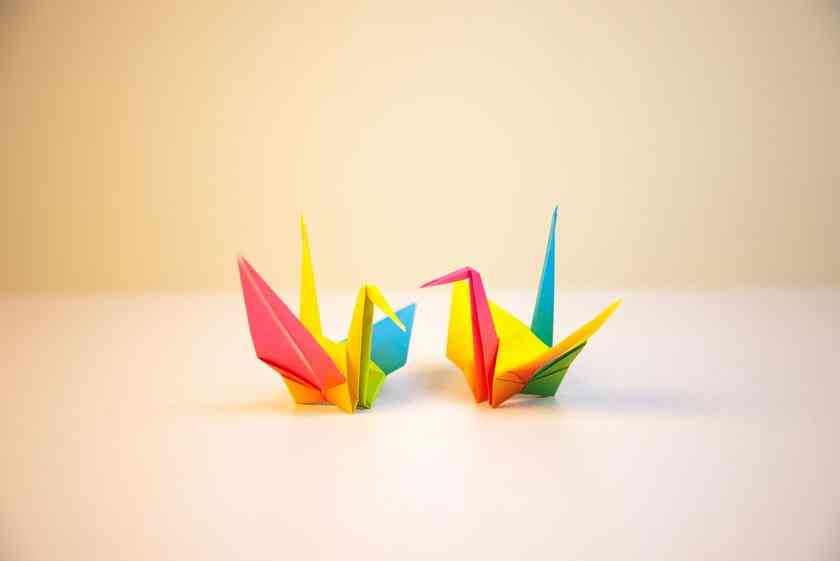
1 葬儀が終わったら、もうぐったり
私の父は癌でした。遠くない将来に見送る覚悟はできていましたが、相続に関してはぼんやりとしたイメージしか持っていませんでした。実際にその時がおとずれ、看取り、葬儀、供養と進むと、それだけで精神的にも肉体的にも疲れてしまい、次第に相続に関しては専門家に依頼しよう、と考えるようになりました。
父の死亡、葬儀の執行、四十九日の法要と納骨、返礼品の手配…。後から思うと覚悟できていたのは父の「死」そのものだけ。亡くなった「後」の行事や手続きがこんなに大変だなんて思いませんでした。父の遺族は、母、兄、私の3人。3人で手分けしてやればいいと簡単に考えていたのですが、母は体調を崩して寝込み、兄は事務的なことは苦手。結局私が一人で葬儀屋さんやお寺さんと話し合い、葬儀から納骨までを手配したのです。なんとか葬儀に伴うやるべきことは終了した頃には私はもう精神的にも肉体的にもぐったりしていました。
2 お金がかかってもいいから、私も楽になりたい(笑)
葬儀関係が終わると、相続に関することに取り掛かる段階になりました。実は父は小規模ですが不動産経営をしており、加盟していた「青色申告会」から相続手続きには期限があることを知らされていました。でも母は「そんなに急いでやらなくても」、兄は「俺は細かいことはわからないから」と、どちらも乗り気ではありません。ネットで情報を探すと「相続手続きは大変だから専門家に依頼しましょう」という書き方ばかり。もう疲れているし、お金がかかってもいいから、私も楽になりたい。誰かに間違いなくやって欲しい。心の底からそう思いました。
3 最低でも100万!?信託銀行に相談すると意外な反応が…
そこで以前からお付き合いのあった、ある信託銀行に連絡をとりました。自分なりにまとめた父の相続財産一覧を持参して、見積もりを作ってもらうことになりました。1週間後に再会した担当者さんからの返答は意外なものでした。
「この遺産相続については、概算ですが相続税がかかりません。それなのに、当行にご依頼いただくと、最低でも100万円の費用を頂戴します。弁護士や司法書士、税理士への依頼金額は別にかかります。非課税で済む相続に、そんなに費用をかけるのはもったいない。ご自身で相続手続きをすることをおすすめします。調べればご自身でも必ずできますよ」
茫然としました。相続手続きって専門家の領域じゃないの?素人の私でもできるの?どうやって?何から手を付けたらいいの?・・・・頭の中がぐるぐる回り、どうやって信託銀行から帰宅したか、覚えていません。
4 相続手続きは素人でもできる!?
専門家である信託銀行の人から「自分でできますよ」と言われてしまい、体よく追い払われたように感じて、目の前が真っ暗になりました。でも、ゆっくり考えてみたら、確かに何らかの公的な免許がなければしてはいけない、例えば法廷弁護などではありません。もしかしたら自分でもできるかもしれない…考えているうちにチャレンジ精神がふつふつとこみ上げてくるのを感じました。
確かにそもそも相続税が非課税であるならば、100万円を超える費用をかけるのはもったいない。ようし、自分で相続の手続きをしよう、と心に決めました。手間はかかっても、自分でやれば費用は最低限になります。
実は父名義の不動産は数か所に分かれていました。試しにいくつかの司法書士事務所に聞くと、それぞれの不動産を管轄する登記所ごとに名義変更手続きが必要になるため、出張料金がかかると言います。司法書士事務所によって、その出張料金が10万円だったり5万円だったり、合理的な基準は無いことがわかりました。それならばこれも自分の足で行こう、と決めました。
5 正確な情報は国税庁と法務局で
情報は主にネットから検索しました。弁護士や司法書士事務所の情報は手順の参考にしましたが、肝心なところは法務局や税務署の情報を参考にしました。専門家に頼まない以上、公的で、直接相続手続きに関わる機関の提供する情報が一番正確だと思ったからです。
こうして情報を得ていくうちに、相続手続きは大きく2つのカテゴリに分けて考えられることがわかりました。1つ目は「相続税の申告」。2つ目は「不動産の名義書換」です。
6 不動産の価値を算定する
相続手続きの1つ目、「相続税の申告」にあたって、貯金などの金融資産と違い難易度が高いのが不動産です。
まず父の残した不動産の価値を算定しました。不動産の価値基準には、実際に近隣の土地が売買された際の相場(以下、実勢価格)と、固定資産税の基準となる固定資産評価額、さらに路線価など複数の基準があります。「土地」の相続に関しては、このうち路線価を使うことを国税庁のサイトで突き止めました。
「家屋」については、毎年所管の自治体から通知される固定資産評価額であることもわかりました。この時、それぞれの自治体から固定資産評価証明書を取得しました。
次に父の不動産がある場所の路線価をそれぞれ調べました。これは所管の法務局に行かなくても、国税庁のサイトで路線価を調べることができました。
こうして相続対象となる父名義の不動産(土地・建物)の価値がわかりました。預貯金は簡単に金額を把握でき、賃貸ビルを建てた時のローン残高も、年2回通知される残高表からわかりました。また父は高価な書画・骨董、車などを持っていなかったので、『(不動産+預貯金)―ローン残高=相続財産』と計算できました。
7 母・兄・私で遺産分割を協議
財産一覧を前に、母・兄・私の3人で、誰が何をどれだけ相続するかを話し合い、その結果を遺産分割協議書にまとめました。父のように遺言を残していないケースでは、相続には「遺産分割協議書」が必要なのです。幸いなことに、兄や私の配偶者からの注文も無く、法定相続分とは多少異なる分割案について、すんなりと協議が終わり、ほっとしました。
遺産分割協議書のひな型は、法務局のサイトでダウンロードしました。
遺産分割協議書は人数分の+3のコピーを用意しました。不動産の名義変更と相続税の申告の際に必要かな、と思ったからです。それぞれに署名と実印での押印、割り印をします。実印を使っているので、全員の印鑑証明書を、作成した遺産分割協議書6通分用意しました。
8 生まれてから死ぬまでの、父の戸籍をたどる
次に私たち3人以外に相続人はいないことを証明する書類が必要です。これが無いと遺産分割協議書は有効性が疑われます。また不動産名義変更にはこの戸籍ひと揃えが必要です。なぜなら私たちの知らない時に父が結婚をしていて、子供がいた場合にはその子供も相続人になるからです。そこで父の戸籍に関しては、できるだけ古くと思い、生れてから死ぬまでの戸籍を揃えました。
まず死亡した時の戸籍から、どこの自治体から本籍を移転させたかを把握します。移転元の自治体に電話で戸籍謄本を送ってもらうように依頼し、既定の料金と返信用封筒を送ります。送られてきた戸籍から、さらにその前にも本籍の移転があったか、それはどこからだったかを調べます。これを数回繰り返しました。
たどり着いた最も古い戸籍は、大分県のある村に出されていたものでした。父は昭和四年生まれで、出生届は祖父の故郷である大分で出されていたのです。私は父が生まれたのも幼少期を過ごしたのも東京の新橋と聞いていました。明治生まれの祖父が若い頃に大分から上京し、新橋で長く事業を営んでいたとも聞いていたので、まさか父の出生届が祖父の故郷、大分に出されていたとは夢にも思っていませんでした。今では町村合併によって全く違う名前の自治体から父の出生時の戸籍を取り寄せ終えた時は、戸籍取得を始めてからなんと2か月以上かかっていました。
また戸籍謄本、除籍謄本、戸籍の附票、改製原戸籍、と聞きなれない同じようなことばが出てくるので、そのたびに自治体の窓口担当者に確認をしました。
相続人である母・兄・私の戸籍謄本も、遺産分割協議書の作成枚数と同じく6枚通ずつ取得しておきました。
9 相続税とその申告
相続税は非課税ということに
父の戸籍を取り寄せる一方で、遺産分割協議書に従って、母・兄・私が、それぞれ金額にしていくらを相続することになるかを計算しました。相続税を支払わなければならないかを調べるためです。
母は配偶者なので、自動的に父の財産の半分は非課税で得られます。兄と私が問題でした。けれどもローンがまだ残っていたおかげで、遺産にかかる基礎控除額内で収まり、私の計算上では相続税は非課税であることがわかりました。
非課税でも申告しなければならない
私の計算上では相続税は非課税であるとわかりましたが、いったん税務署に相続税についての計算書を持参し、念の為の確認してもらいました。問題なし、との答えをもらって安心したのを覚えています。それまではネットの情報だけが頼りで、誰にも相談できなかったので。今思うと、もっと早くから税務署に相談すれば良かったな、と思います。相続税の申告書類と、用意する資料一覧ももらい、申告に向けて準備をしました。
重要なポイントは相続税が非課税、と自身で計算した上でわかっていても、税務署には申告が必要だというところです。税金の申告は「課税対象者だけが必要なこと」と考えがちかもしれません。しかし相続税が計算上は非課税の場合でも、税務署に申告をしなければ、なぜこの遺産相続では相続税が非課税という計算結果になったかは税務署にはわかりません。税務署は全ての情報を税金の申告書から確認するためです。
相続税の申告書には、父のプラスの遺産(不動産など)とマイナスの遺産(ローンなど)の内訳や金額を全て書きました。葬儀にかかった費用の一部はマイナスの遺産同様に扱われます。そして相続財産額が相続税の基礎控除額以下なので、この件は相続税が非課税になりました、と申告書で税務署に提出しました。
A 相続財産=プラスの遺産(土地・家屋・預貯金など)-マイナスの遺産(ローンなど)-葬儀費用
B基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数*平成27年改正)
A>B → 相続税が発生
A<B → 相続税は非課税
最終的に母・兄・私3人分の相続税を申告したのは、死亡後6か月目でした。「専門家の力を借りず、期限までに良くまとめましたね」。税務署の職員さんにとっては特別なことばではなかったかもしれませんが、私は「苦労をわかってもらえた。やっと一つ終わった」と、涙が出るほどうれしかったです。
10 故人も確定申告!…準確定申告
父は青色申告をする小規模事業者だったので、死亡から4か月以内に準確定申告が必要でした。死ぬ前に得た収入を申告し、経費を引いて所得を割り出し、納税額を決めるのです。これは事前に経費や収入の書類を揃えて、毎年の青色申告と同じことをすればいい手続きに似ていました。そのため父の生前から青色申告を手伝っていた私には楽な作業でした。税務署に直接出向き、準確定申告をしました。
11 不動産の名義書換(相続登記)
相続税の申告を準備する傍ら、相続手続きの大きなカテゴリとしての2つ目、不動産の名義変更を準備しました。法務局のネット情報を調べ、膨大な量の父の戸籍と、母・兄・私の戸籍謄本、遺産分割協議書、不動産登記情報証明書(以前の登記簿謄本)などを揃えて、所管の法務局(いわゆる登記所)へ相談に行きました。
「素人がやるなんて無理なんだよ」
相談の際には相談係員さんを選べません。順番に呼ばれたブースで、そこにいる相談員さんとお話をします。私の担当になった方は、なぜか会った時点で既にご機嫌が悪く、私の書類の不備をあげます。「でも、そんな書類が必要とは、この法務局のサイトに書いてありません」というと、「じゃあ、書類を出してみればいいだろ。どうせ通らないんだから。第一素人がやるなんて、無理なんだよ」とまで言われてしまいました。
そんな風に言われると、私は凹むより、余計に燃えるタイプです(腹は立ちますが)。「ようし、絶対に書類を揃えて、黙らせてやる!」と市役所へUターンしてまた書類を集めました。さらに要求された人物関係図までWORDで作成し、即日、再度相談窓口へ。すると先ほどの人が「さっきはすみませんね。直前の人が面倒で、揉めてしまったので、腹が立っていたから・・・」と謝ってくれました。
1か所クリアすると、後はすっかりスムーズに
こうして相談窓口でOKをもらい、ようやく最初の法務局で申請窓口に書類を出すことができました。2か所目と3か所目はもう内容がわかっているので、法務局を訪ねていき、書類を出すだけでした。
不動産の名義変更は、申請書類を出してから基本的に2週間以内に連絡がなければ、問題なし、ということでした。私は書類提出から2週間、どこかの法務局から連絡が入るんじゃないか、とドキドキしていました。けれどもどこからも、何の連絡もありませんでした。
そして申請書類を提出してから2週間後に、再度それぞれの法務局へ出向き、新しい不動産登記情報証明書を申請しました。所有者の変更がされた書類を見つめて、肩の荷を下ろしたのは、父が亡くなってからほぼ10か月目でした。
12 生前よりも父や祖父をより身近に…自分でする相続手続きの最大のメリットとは
費用面のメリット
相続手続きを自分でやることの実質的なメリットは費用の面です。専門家に依頼しなかい分、費用は大きく抑えられます。誰がしても必要な、国が定めた手数料だけで終えることができました。
もっと大きなメリット
費用面ばかりに目が行きがちですが、私にとって相続手続きを自分でした最大のメリットは費用ではありません。父や祖父母、叔父など、既に亡くなった人たちを、より身近に感じられるようになったことです。
父の戸籍を遡っていく過程で「あ、お父さんが暮らしていたころは、新橋は『芝区』だったんだ」とか、「あれ、おじいちゃんとおばあちゃんは、同じ大分でも違う村出身だったんだ。同じ村って聞いていたのに」「早くに亡くなったおじさんの名前は『登志夫』だったんだ。私と『登』が同じだ」など、知らなかったことがたくさんわかりました。
相続手続きをする前は「亡くなった人達」とだけ考えていた人たちが、生き生きとした存在として感じられ、自分と繋がっていると実感できました。これが私にとって、自分で相続手続きをした最大のメリットです。
もしいつか父に会うことができたら「お父さんは芝区の小学校に通ったの?」とか「おばあちゃんはどうやっておじいちゃんと出会ったの?」など、聞いてみたいことたくさんできました。
専門家に相続手続きを依頼していたら、手間もかからず、費用だけ払えば簡単にできたのだと思います。その代わりに、こうして家族の繋がりを感じることは難しかったのではないかと思います。今、改めて祖父の世代から父、私と繋がっていることを感じられ、生前よりも身近に父や祖父母を感じられるようになったのは、相続手続きを自分でしたからです。簡単なことではなかったけれど、やってよかった。今、本当にそう思います。