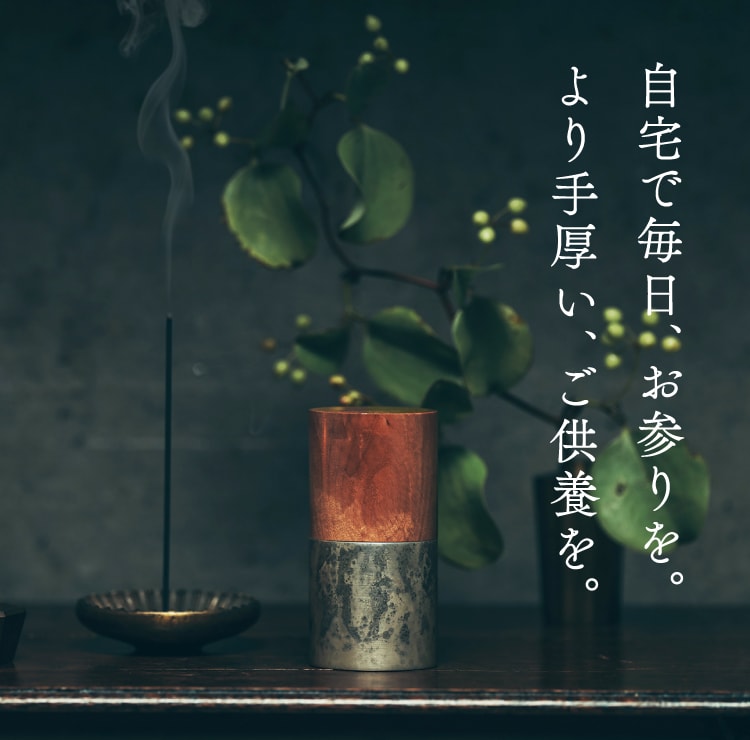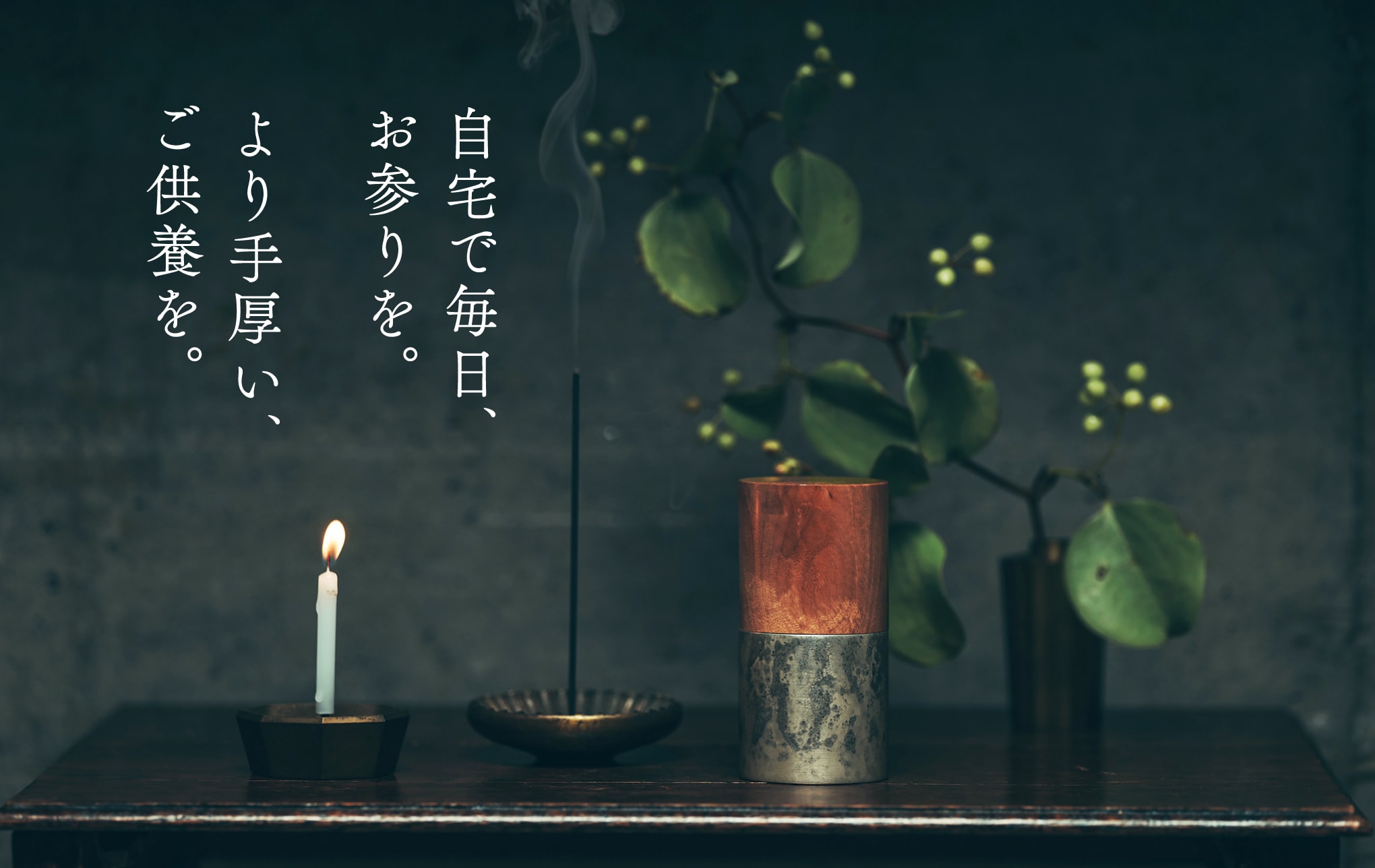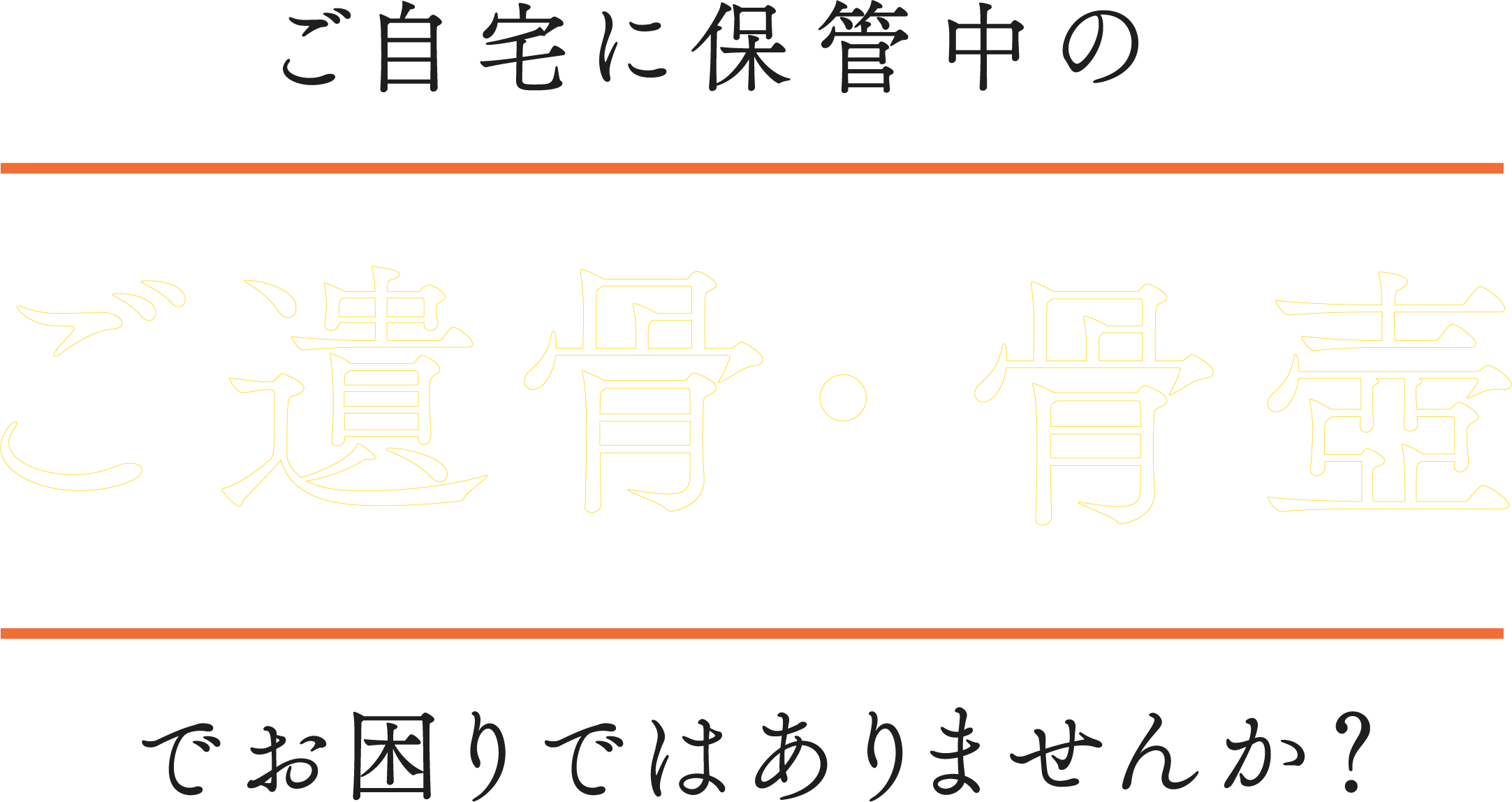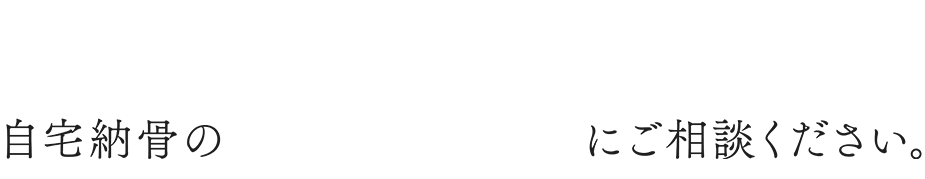筆者は、都内の葬儀社に5年勤務した後に関西へと移住し、引き続きエンディング業界に従事していますが、これまで当たり前だと思っていた東京の葬儀が、他の地域と比較してみると、いかに独特でユニークかということを思い知りました。そもそも葬儀というのは今でも地域性が色濃いものなのですが、これは国歌や宗教による儀式の先導と同じくらいに、民間習俗として地域それぞれの葬儀が各地の民衆たちの手によって発展、定着してきたからだと思われます。この記事では、「東京の特殊性」としての葬儀事情をご紹介いたします。
ここが違うよ東京の葬儀 ―独特といえる東京の葬儀事情

1 東京がむしろ独特であるという事実
東京の葬儀が他と比べて独特なのは、東京という場所そのものが、他にはない独特の都市だからです。首都東京の葬儀の特殊性に影響を与えている要素としては、次の3つが挙げられます。
- 圧倒的な人口の多さ
- 地方出身者の多さ
- 地域や寺院とのつながりの希薄さ
まずは、それぞれのポイントを簡単に予習して、それがどのように葬儀に影響を与えるのかを確認しておきましょう。
1-1 圧倒的な人口の多さ
東京は日本の首都であり、政治、経済、文化の中心地です。2019年4月1日現在の東京都の人口は、1380万人を越え、これは日本の人口の1割強にあたる規模です。人口が多いということはそれだけ葬儀件数も多く、それに比例するように火葬場や葬儀業者の数が多いという特徴が見られます。
1-2 地方出身者の多さ
人口が多いだけではなく、地方出身者の流入が多いという点を見逃してはなりません。国立社会保障・人口問題研究所が行なった「第8回人口移動調査」(2016年)(※)によると、東京都に住んでいる人で、生まれが都内の人は54.4%、東京近郊の三県(神奈川・千葉・埼玉)の人は10.0%、これらに該当しない35.6%が地方出身者にあたります。喪主や親族が地方から上京してくる、あるいは東京では火葬だけして故郷に遺骨を持って帰るなどは、東京の葬儀現場では日常茶飯事のことなのです。
1-3 地域や寺院とのつながりの希薄さ
東京に住む人たちのライフスタイルは実に多様です。仕事や趣味などを介して独自のつながりやコミュニティを作り上げている半面、地域のつながりは希薄な傾向にあります。葬儀を考える上で寺院とのつながりというのは一般的に地方では重要な要素ですが、東京では地方出身者が多いこともあり、普段からお寺と接点を持つような人は少ないのが実状です。よって多くの人たちが、葬儀を行おうとするときはじめて、葬儀社に寺院を紹介してもらう、ということになります。葬儀や仏事の簡略化も東京では顕著のように思えますがそれもこういった背景が影響しているといえるでしょう。
東京の特殊性をご理解いただいたところで、いよいよ東京の葬儀事情をご紹介して参ります。
2 東京の火葬場は民間経営 火葬料金の相場も高い
公共インフラでもある火葬場は、日本全国を見渡してもほとんどが自治体によって運営されている公営の火葬場ですが、東京都、とりわけ23区内では民間経営の火葬場が主流です。これは全国的に見ても極めてまれなケースです。どうして東京だけ際立って民間企業によって火葬場が営まれているのでしょうか。
2-1 23区内は9ヶ所の内7ヶ所が民営火葬場
東京23区には9カ所の火葬場がありますが、その内の7カ所が民営です。町屋、四ツ木、桐ケ谷、幡ヶ谷、落合、堀之内の6つの火葬場を経営するのは東京博善株式会社。もうひとつの民営斎場は板橋区にある戸田葬斎場です。
ちなみに公営斎場は東京都が運営する瑞江斎場(江戸川区)と、5つの区(港区、品川区、目黒区、世田谷区、大田区)による共同事業で運営されている臨海斎場があります。
日本環境斎苑協会の集計によると、2018年8月現在の全国の火葬場の数1457ヶ所のうち、公営火葬場は1409ヶ所で全体の96.7%あるのに対し、民間企業が経営する火葬場はわずか15か所、全体の1.0%です(※)。
2-2 東京23区の火葬場を寡占する東京博善と木村荘平
23区内で6つの火葬場を経営する東京博善株式会社とはどのような企業なのでしょうか。
江戸時代、火葬は主に寺院の境内で行われていましたが、明治に入り、埋葬地の不足や公衆衛生の問題が浮上。そこに商機を見出したのが実業家であり政治家の木村荘平でした。木村は、日暮里村の火葬場運営を請け負う形で東京博善の前身を設立しています。その後、火葬場施設としての公益性を重視するために宗教者による経営を経て、現在は中堅出版社の廣済堂グループの傘下にあります。
公共インフラである火葬場経営を民間企業が担うということを不思議に感じる人もいるかもしれません。通常火葬場は、住民の反対などで土地を定めるのが難しく、また設備投資も大きいいので採算面でも難しい事業だと思われています。だからこそ公営が多いと想像できるのですが、しかし逆に全国でも類を見ない超過密都市の東京では、豊富な人口(=市場)を背景に、民間でも事業運営が成り立ちやすいともいえます。そこに木村荘平という知る人ぞ知る明治の怪傑事業家の手腕も重なったのかもしれません。
2-3 23区外は公営火葬場が目立つ
ちなみに、目を東京23区外に向けてみると、民営火葬場は日華多磨斎場(府中市)と、足立区民が利用する谷塚斎場(埼玉県草加市)くらいで、あとは公営火葬場です。ひとつの自治体がひとつの火葬場を運営しているものと、複数の自治体が広域連合を設立して共同運営するものがあります。
2-4 23区内の火葬料金は高い
下の表は、代表的な都内の火葬場とその料金についてまとめたものです。
| 火葬場 | 場所 | 火葬料金 |
|---|---|---|
| 東京博善(6カ所) | 23区内 | 59000円 (※火葬炉は最上等) |
| 戸田葬祭場 | 板橋区 | |
| 多摩葬祭場 | 府中市 | |
| 谷塚斎場 | 草加市 |
| 火葬場 | 場所 | 火葬料金 | |
|---|---|---|---|
| (住民) | (住民外) | ||
| 瑞江斎場 | 江戸川区 | 61,000円(都民) | 73,200円 |
| 臨海斎場 | 大田区 | 40,000円 | 80,000円 |
| 南多摩斎場 | 町田市 | 0円 | 50,000円 |
| 八王子市斎場 | 八王子市 | 0円 | 50,000円 |
上の表からは次のことが分かります。
民営火葬場は火葬料金が高い
公営火葬場と民営火葬場に比べると、民営火葬場の方が費用が高いことが分かります。
公営火葬場も23区内は火葬料金が高い
23区内の瑞江斎場と臨海斎場は、公営斎場にも関わらず火葬料金が割高です。これは東京博善をはじめとする同一エリアの火葬料金相場(59,000円)にあわせた価格設定だと思われます。
23区外の公営斎場は火葬料金が0円
23区外の公営料金はなんと0円。これは、火葬場の運営がその地域住民の税金によって運営されているからです。ですから住民外の火葬料金はそれなりに高額な費用が設定されています。
ちなみに東京近郊の主要都市や全国の主要都市の火葬料金は次の通りです。
| 火葬場 | 場所 | 火葬料金 | |
|---|---|---|---|
| (住民) | (住民外) | ||
| 浦和斎場 | さいたま市 | 7,000円 | 56,000円 |
| 横浜市各斎場 | 横浜市 | 12,000円 | 50,000円 |
| 千葉市斎場 | 千葉市 | 6,000円 | 60,000円 |
| 札幌市各斎場 | 札幌市 | 0円 | 49,000円 |
| 名古屋市各斎場 | 名古屋市 | 5,000円 | 70,000円 |
| 大阪市各斎場 | 大阪市 | 10,000円 | 60,000円 |
| 刻の森福岡市斎場 | 福岡市 | 20,000円 | 70,000円 |
全国的に見ても、公営火葬場の火葬料金は0円から1万円程度です。このようにしてみると、いかに東京の火葬料金が高額かお分かりいただけると思います。
3 東京は自社会館を持たない葬儀社が多い
前章では東京の火葬場についてご紹介しましたが、葬儀社と斎場についても東京は特殊です。東京には、自社の葬儀会館を持たない葬儀社がたくさんあります。これは現在においては、地方ではあまり考えられないことです。地方ではほぼ「葬儀社=葬儀会館」を意味します。自社会館は葬儀社にとっては最大の設備投資であり、経営における生命線でもあります。もちろん都内にも会館を保有する葬儀社はありますが、それ以上に会館をも持たない葬儀社が乱立しているのです。
3-1 寺院が経営する「貸し会館」の存在
ではどうして会館を持たない葬儀社でも経営を続けられるのかというと、東京都内には逆に、様々な葬儀社・喪主に貸し出される貸し会館(葬儀専用会館)が数多く存在するからです。それらの多くは葬儀社でなく、寺院が経営しています。地方にも公営斎場のように誰もが使用できる葬儀式場や「場所だけ貸す」という寺院などもあるにはありますが、やはり主流は葬儀社の保有の会館です。
東京の葬儀社は、葬儀の仕事が入ると喪主と打ち合わせをして、葬儀会館を予約します。葬儀当日には会館の中に自前の祭壇などを持ち込んで飾り付けしなければならず、都内の葬儀社は大変慌ただしい中、葬儀の準備を進めます。
3-2 電話とパソコンがあれば開業できる
都内の葬儀社は自社会館を保有していなくても葬儀の請負が可能です。よく冗談のように「電話とパソコンがあれば葬儀社を開業できる」と言われますが、本当にその通りなのです。集客さえできれば(この集客が大変なのですが)、式場も、祭壇も、供花も、料理も、寝台車もすべてアウトソーシングで行なえるのが東京の葬儀業界の特徴です。人口を背景に、市場として高度化・成熟しているといえるでしょう。自社会館を持たずに葬儀社を経営する、このビジネスモデルは地方ではなかなか難しいでしょう。
3-3 喪主としては「まず会館を決める」のが賢い選択
さて、ではこのような東京の葬儀事情を、喪主はどのように賢く利用すればよいのでしょうか。「葬儀社=葬儀会館」の地域では、会館の立地がものを言います。葬儀社の価格やサービスのクオリティもさることながら、やはり家から近い式場、参列しやすい式場が選ばれやすいようです。
一方で、都内のように「葬儀社≠葬儀会館」の場合、まずは希望の葬儀会館を決めて、それから複数の葬儀社を比較検討するのが賢い方法でしょう。いわゆる「相見積もり」です。自社会館ではその葬儀社でしか施行できませんが、貸し会館は原則どの葬儀社でも施行が可能です。だからこそ、複数の葬儀社の中から、価格、サービス、社員の人柄など、さまざまな面を比較検討できるのです。昨今の葬儀業界は競争が激しいため、多くの葬儀社は一都三県であればどこへでも駆けつけるでしょう。
4 東京は全部拾骨 遺骨を全て持ち帰る
東京の火葬場では焼骨をすべて骨壺に納めて家族が持ち帰ります。筆者もずっとそれが当たり前だと思っていました。しかし関西はそうではないのです。遺骨の一部を骨壺に納めると、あとは火葬場が引き取るのです。これには驚きました。骨壺の平均的な大きさは、関東が6~7寸、関西が3~4寸です。関西の人は、「東京の骨壺は大きすぎる」と、目を丸くして驚いています。日常茶飯事です。
4-1 遺骨がお墓に入らない
火葬後に自宅に持ち帰る遺骨の違い。これで一番困るのは、東京で火葬した遺骨を関西のお墓に納骨するときです。つまり、遺骨がお墓の中に入らないのです。
お墓の形は日本全国同じだと思う人が多いでしょうが、実は地域によって微妙な違いがあります。関東と関西では、遺骨を納める場所(カロート)の構造が決定的に異なります。関東のお墓は7寸の骨壺が入る構造になっています。それに対して関西のお墓は関東と比べてカロートが小さいのです。関東で標準サイズの骨壷ではお墓の中に入らないのです。ではどうするのかと言うと、あらかじめお骨を骨壺から出して、手で力を加えて小さく砕いて圧縮していきます。それをさらしの袋の中に入れて(骨壷が入らないので)、そのままカロートに納めます。
ちなみに上記のケースに限らず関西では納骨にあたってさらしの袋がよく使われます。さらしの袋のまま埋葬するのは、お骨を土に還すためです。
4-2 東西の境界は日本アルプス
東西で焼骨の扱いに違いがあるのはなぜなのでしょうか。決定的な根拠は分からないようですが、日本葬送文化学会「火葬後拾骨東と西」では、遺骨の全部拾骨と部分拾骨の境界は、能登半島の根幹部(石川県)から浜名湖の西側(静岡県と愛知県の県境あたり)に抜けるライン、いわゆる日本アルプスを越えたラインだそうです。浄土宗僧侶でジャーナリストの鵜飼秀徳さんのコラム「西日本では"遺骨"を火葬場に残すのが常識」(※)によると、フォッサマグナの左端、糸魚川静岡構造線が東西の文化の境界であることに言及し、葬送のしきたりも東西で異なることに触れています。
5 東京の通夜ぶるまいは、全員に案内
通夜ぶるまいとは、お通夜のあとの食事の席です。東京の葬儀では、親族だけでなく、参列者も通夜ぶるまいの席に案内します。一方関西では、通夜ぶるまいの席に着くのは親族だけ、参列者は焼香を終えて通夜式を終えると帰宅します。
参列者を通夜ぶるまいに案内することで、通夜式の導線が変わります。関西では、参列者各自は焼香を済ませると自席に戻ります。そして通夜式を終えると、喪主が参列者に御礼の挨拶を述べ、そして散会となります。一方で東京の場合は、参列者たちは焼香を終えると自席に戻らずに通夜ぶるまいの席に案内されます。寿司や煮物やオードブルなどの大皿料理が並び、飲み物がもてなされます。これらは喪主から参列者への御礼の気持ちなので、わずかでも口にして帰宅するのがマナーだとされています。
そして、通夜ぶるまいがあるため、費用負担がかさむのは言うまでもありません。ただし最近は葬儀が小規模化しているため、通夜ぶるまいの案内を控えるケースも出ているようです。
6 弔いの簡略化 葬儀の中で初七日法要
地方出身者の多い東京では、仏事もどうしても簡略化しがちです。普段からのお寺とのつながりがない喪主は葬儀社に寺院を紹介してもらいます。するとどのように葬儀や仏事を進めるかは自然と喪主と葬儀社との打合せの中で決まっていきがちです。
6-1 繰上げの初七日法要
通夜のない葬儀「一日葬」はいまや当たり前ですし、死後七日目に行なうはずの初七日法要も、葬儀当日に行なうのが慣例化しています。つまり、死後七日目に行われるべき初七日法要が日数を繰り上げて行われるわけですが、葬儀当日の初七日法要は、さらに次の2つのパターンがあります。
- (A)火葬後の初七日法要
- (B)火葬前の初七日法要(葬儀式の中に繰り込まれる)
(A)は葬儀および火葬の後、式場や寺院に戻って初七日の法要を行います。つまり、葬儀→火葬→初七日、の流れです。会館での葬儀の後、火葬場に向かい、そのあとまた会館に戻ってきます。初七日の法要においては祭壇には故人様の遺骨を安置します。一方で(B)は、葬儀式の中で初七日法要の読経もいただくというものです。つまり葬儀→初七日→火葬、の流れです。会館で葬儀も初七日も済ませたあとに火葬場に行くので、会館に戻る必要がなくなり、より合理的な流れになります。
東京は葬儀件数が多いため、火葬場の予約枠に合わせて葬儀を進めなければなりません。遅刻は許されないのです。また、葬儀会館も次に通夜を控えている葬家のために速やかに明け渡さなければなりません。葬儀社、寺院、火葬場の都合などから、初七日法要の繰り上げ(または葬儀繰り込み)は当たり前になっています。合理性がどんどん優先されているのです。
6-2 七日ごとの中陰法要も省略される
葬儀を終えたあとも、四十九日法要までは七日ごとに中陰法要を執り行い、僧侶が自宅にお参りに来るものです。こうした仏事は少なくなってきたとはいえ、関西ではまだ行われていますが、東京ではめっきり見かけません。葬儀の簡略化は日本全国に見られる風潮ですが、東京においては特にその流れが顕著なようです。
7 都市部に多い直葬
直葬とは、通夜や葬儀のようなセレモニーを執り行わずに、火葬のみを行なう葬儀スタイルのことです。鎌倉新書が2017年に行なった「第3回お葬式に関する全国調査」(※)によると、直葬を選ぶ人の割合は全体の5%だったそうです。これを東京都に限定すると9%にも及び、他の地域に比べて東京は直葬が多い地域であることが分かります。
直葬が多い理由には、経済的に余裕のない人、葬儀を不要と考えている人、身寄りのない人などが直葬を選んでいるからと思われます。これに加えて東京都はじめとする都市部に直葬が多いのには、葬地方出身者が多いという理由が考えられます。
故郷にお寺やお墓を持つ人が都内で亡くなった場合、都内で葬儀や火葬を行って遺骨を故郷に持って帰る。あるいは遺体を搬送して故郷で葬儀を執り行うといういずれかを選ぶことになります。費用と手間の負担から、選ばれているのは前者でしょう。
ところ変われば葬儀のしきたりも変わるものです。古くからの地域性に加えて、首都という独自性が、東京独特の葬儀事情を生んでいることがお分かりいただけたかと思います。今後日本はさらに少子高齢化が進み、都市部への人口流入が加速すると思われます。弔いの合理化は避けられないのかもしれませんが、そんな中でも心の込もった葬儀や弔いをしていきたいものです。