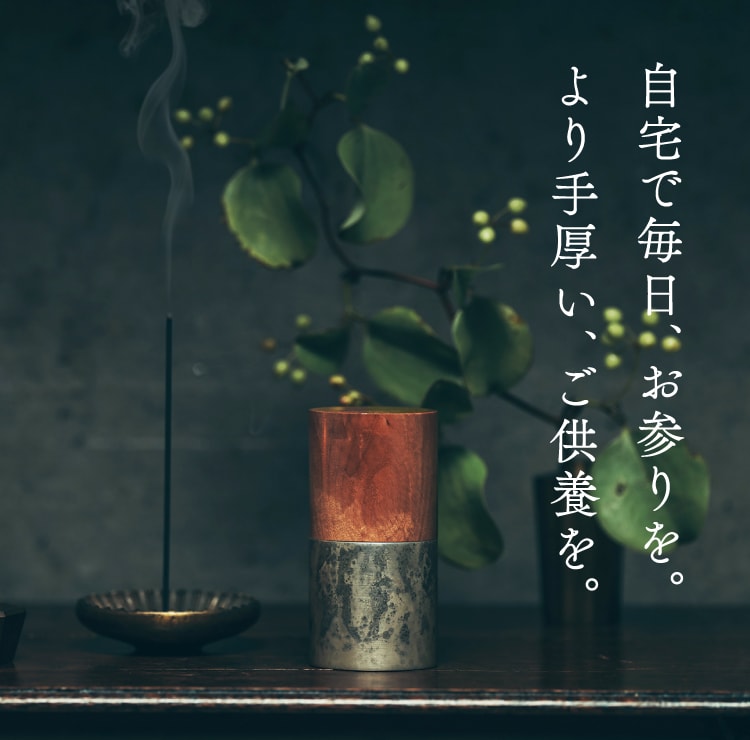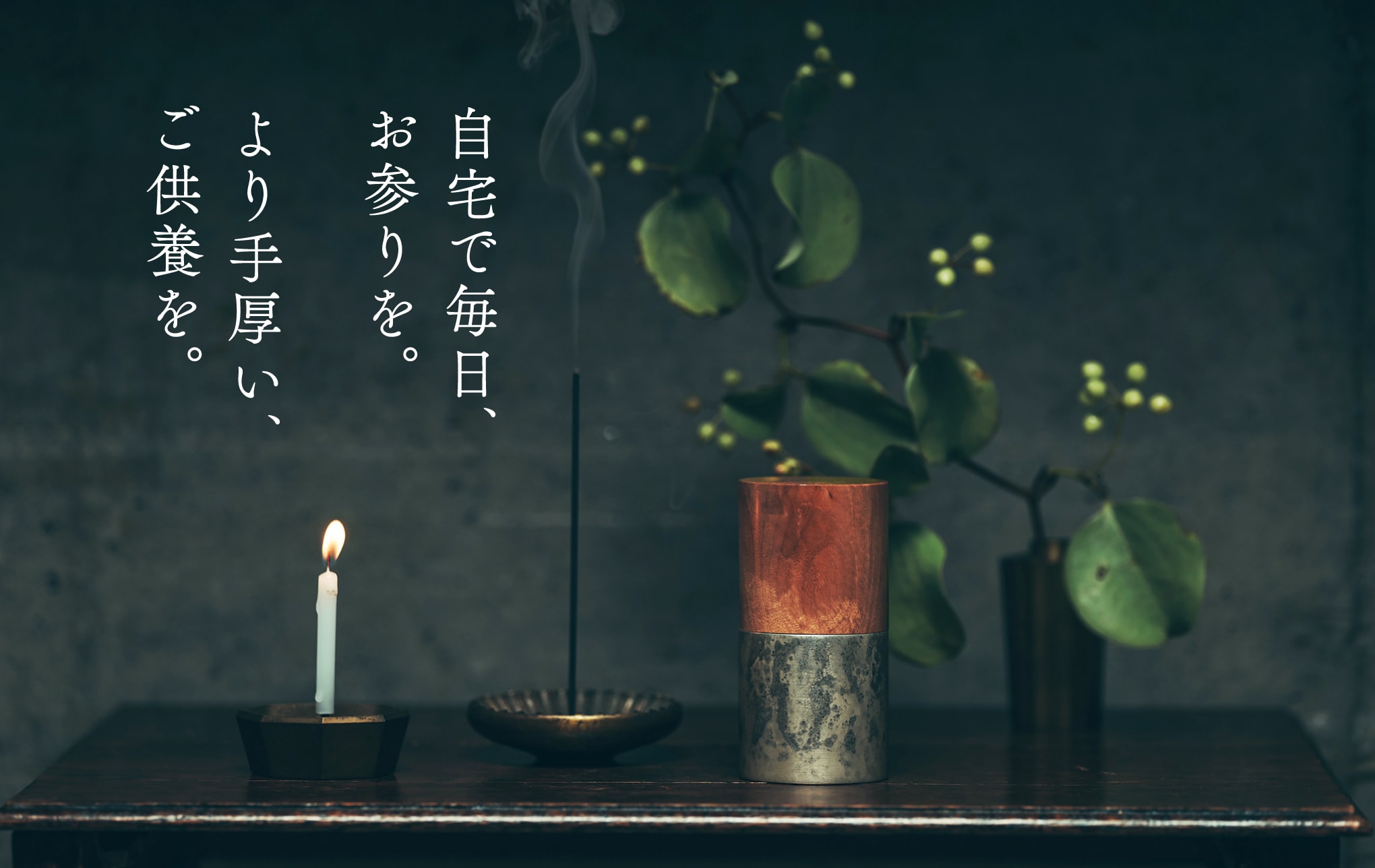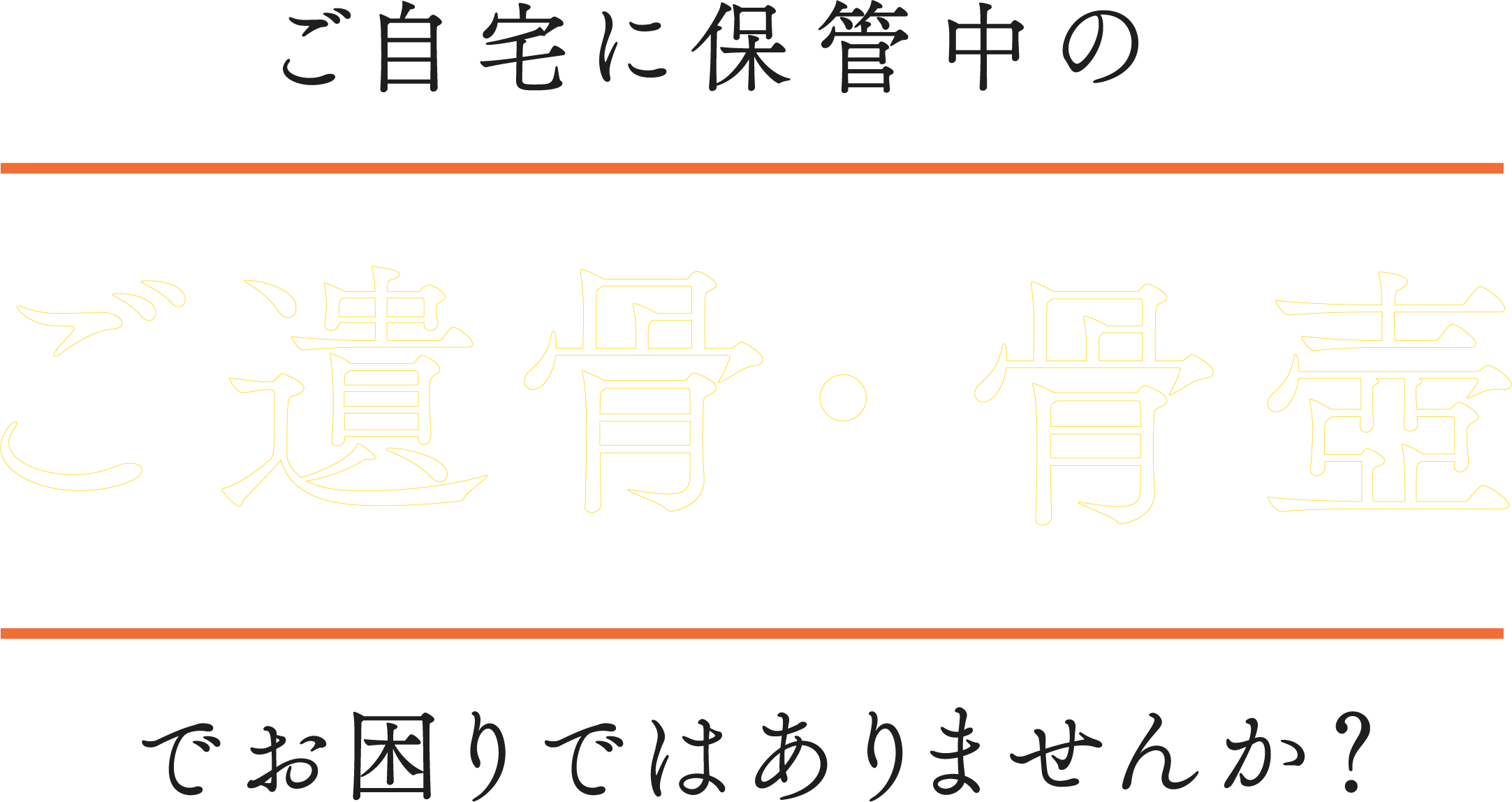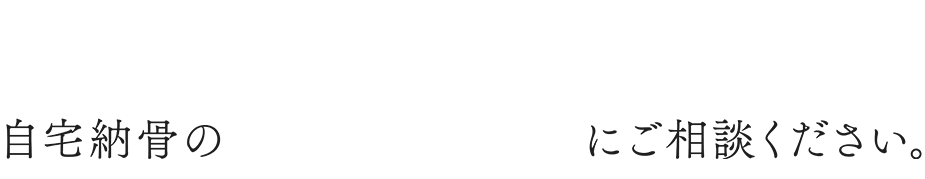近年、自分の人生の終わりに向けて活動する「終活」が注目されています。元気なうちに身の周りの持ち物や財産をすっきりさせて、ゆったりとした老後を過ごしたいと考える方が増加しているのも一因のようです。今回は終活のひとつ「生前整理」について紹介します。自分の死後に家族へ負担をかけないためにも、生前整理は必要です。生前整理を始める時期や進め方についてもチェックしましょう。
生前整理の意義と進め方
1.生前整理について
終活のひとつである「生前整理」とはどのようなものなのでしょうか。
生前整理とは
「生前整理」とは、時間的にも体力的にも余裕がある元気なうちに、身の回りのものを整理しておくことをいいます。生前に身の回りの財産や持ち物を整理することで、自分の死後に遺族が相続で争ったり、遺品整理の負担がかかったりするのを防ぎます。現在ひとり暮らしの方や将来施設へ入居予定の方はもちろん、夫婦まだ元気なうちでも、いざというときのために早めに備えておきたいものです。
生前整理を始める時期
生前整理はいつから始めても構いません。20代、30代でも生前整理を始めるのに早すぎるということはないのです。だれもが事故や災害、病気などにより、突然亡くなる可能性があります。
また歳を重ねてから慌てて整理しようとしても、思うように体が動かなかったり、作業中にケガをしたりする恐れがあります。さらに認知症などが進むと正常な判断がしづらくなり、遺言書の作成が大変です。自分の望むかたちとは違う整理になってしまう可能性もあります。もしものときに備えて、生前整理は早いうちから始めるといいでしょう。
2.生前整理の意義
生前整理は「残された遺族のため」に、そして「自分のため」にも必要なことです。
残された遺族のために
遺品整理の労力
亡くなった方の遺品整理や財産の相続手続きは、通常は子どもや配偶者などの家族が行います。本人が死後の準備をすることなく亡くなった場合は、故人の想いに関係なく家族が判断しながら一つ一つの遺品について整理するため、非常に労力がかかります。
家族間のトラブル防止
さらに遺品整理や相続の過程で、家族間のトラブルに発展するケースも多いです。生前整理をすることで、遺族の負担やトラブルを減らすことができます。元気なうちに自分が必要なものだけを残して断捨離を行い、財産や物を整理することで、死後の遺族の負担を大きく軽減することができます。
自分のために
自分の希望を叶える・意思表明をしておける
死後の準備をすることなく死亡した場合、遺品の整理を家族が独断で行うことになるため、故人の想いとは異なる方法で処分される可能性があります。生前に財産の相続や分配、身の回りの整理をして、自分の希望のとおりに遺品整理をしてもらう手配をしておけば、死後についての憂いをなくすことができるのです。
断捨離して快適に
生前整理は断捨離の絶好の機会とも考えられます本当に必要なものだけに囲まれたシンプルな生活の中で毎日を過ごすことができます。この先の将来をより快適に生きていくためにも非常に意義深いものとなるでしょう。
3.生前整理の注意ポイント
少しずつやる
生前整理は体力も精神力も必要です。自分の財産をだれにどれだけ分配するか悩んだり、物を整理し処分したりするのに労力がかかります。ポイントは一度に全部整理しようと思わないことです。時間をかけて少しずつ整理していきましょう。
業者を頼る場合は複数検討を
粗大ごみなどを処分する場合は、ごみ処理費用がかかります。また労力がかかる生前整理は業者に依頼する方法もありますが、業者に頼めば費用がかかります。生前整理を負担に感じる場合は、すべて業者に頼むのではなく、自分で整理しつつ部分的に業者を頼る方法もおすすめです。ただし業者の中には悪徳業者も存在します。高額請求をしたり、価値のあるものを安く買いたたいたりする手口があります。契約する前に複数社検討してから業者を選びましょう。
4.生前整理の進め方
前整理では主に「物」と「財産」の整理をしていきます。何がどれぐらいあるか把握し、必要に応じて処分しましょう。
必要なものと不要なものに分ける
自分の死後に物が大量に残っている場合は、遺族が整理して処分することになり、大変な労力が必要です。まずは「必要なもの」と「不要なもの」に分けます。これから先の生活で使うものや思い出のあるものは保管し、長年使用していないものやこれから先の生活で使わないものなど、不要なものは処分しましょう。未使用で捨てられないものは、知人へ譲るなども一つの方法です。
必要なものに囲まれたシンプルな生活をすることで、居心地の良い環境で老後を過ごすことができるでしょう。
財産目録の作成
財産といっても、現金や預貯金だけではなく、家や土地、宝石、骨とう品、車、有価証券などさまざまなものがあります。死後、故人が所有していた財産を遺族が把握することは非常に手間がかかります。どんな財産がどれだけあるのか自分自身で把握し、「財産目録」を作ると、遺族の負担を減らすことができます。
このことで、不要な財産の処分も行いやすくなり、生前贈与などを相続税の対策も検討しやすくなるでしょう。
財産や重要書類の保管場所を伝えておく
空き巣対策で通帳や印鑑などの貴重品をバラバラの場所に保管している方は多いことでしょう。ただしいざという時のために、どこに保管しているか家族には保管場所を伝えておきましょう。
また、不動産や貴重品、保険証書など遺産相続に関係するものは、ある程度まとめて置いておくと、死後に遺族が手続きしやすくなります。
エンディングノートを活用する
死後に家族や大切な人へメッセージを伝えたり、お墓や葬式などの希望を伝えたりすることができるのが「エンディングノート」です。法的効力はありませんが、簡単な指示や希望を家族に伝えられます。また、亡くなる前後に役立つだけではなく家族にとって大切な形見になります。ノートを書くことで、自分自身の人生を振り返ることもできます。
遺言書を残す
法的効力をもたせられない内容を記述することが多いエンディングノートに対して、正しい手順に則って遺言書を作成すると、相続などに関して法的効力を持たせられます。遺言書があることで、遺族間のトラブルを防げる可能性もあります。
財産の相続について希望がある場合は、遺言書を作成した方がいいでしょう。法定相続人以外に財産を相続させたい場合や、特定の人物に相続させたい場合など、財産の相続について指示がある場合は、正式な遺言書がなければ相続させられない可能性もあります。