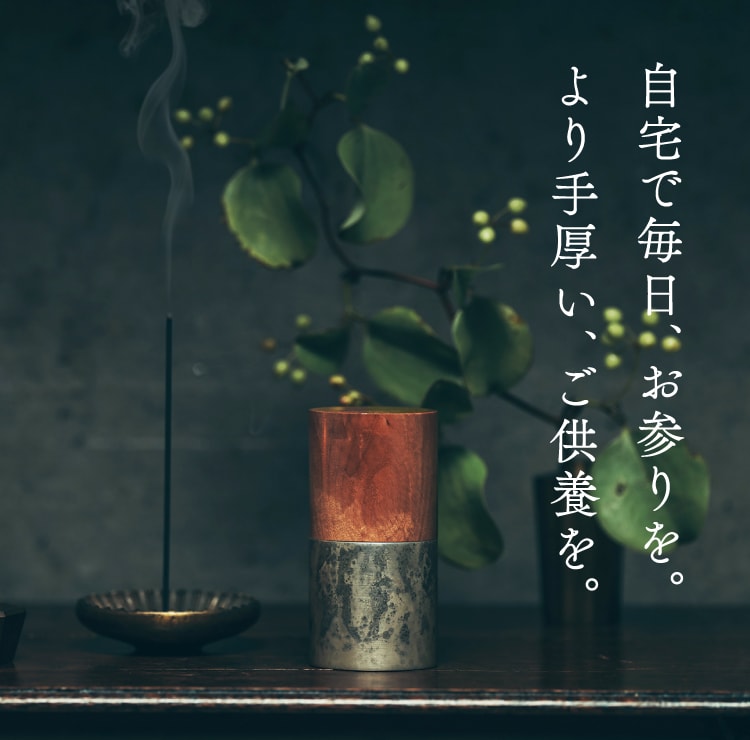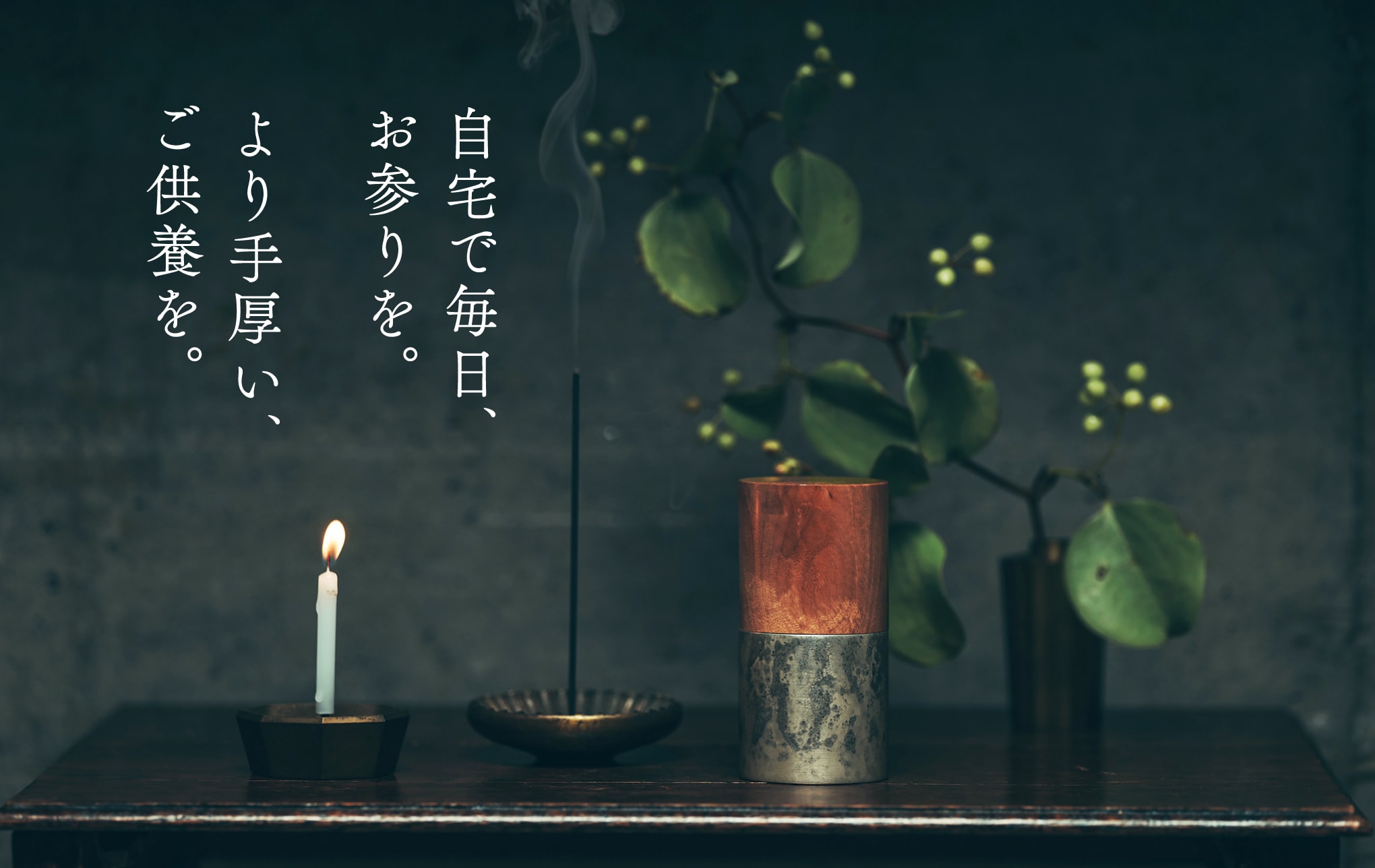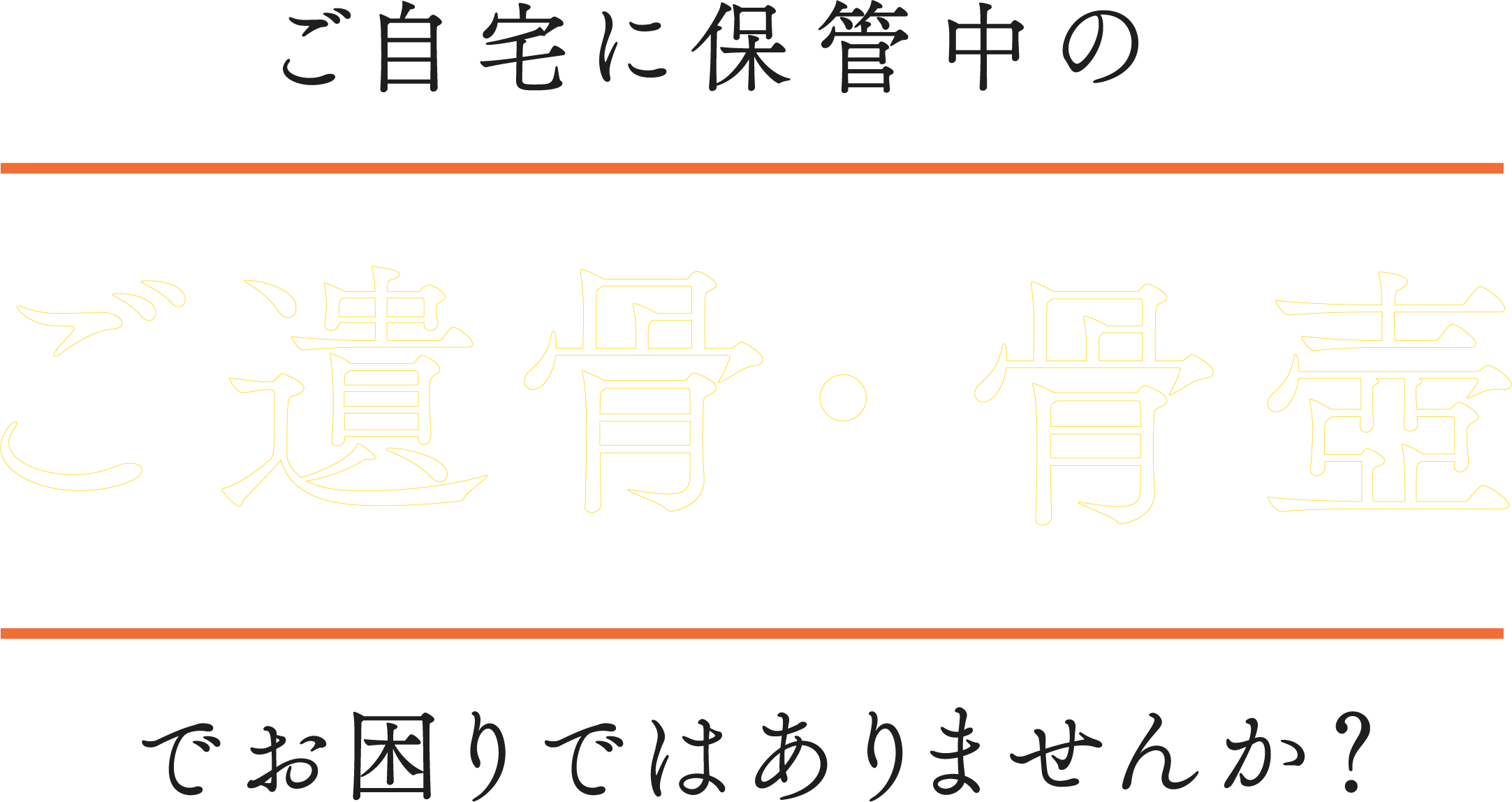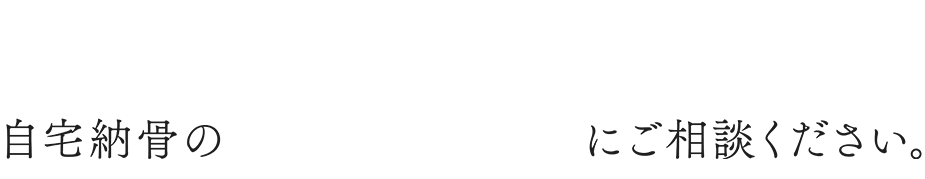相続は人生でたびたび起きることではありません。一連の相続手続きの中に慣れている人はほとんどいないでしょう。特に亡くなった方(以下、被相続人)からの相続を放棄する、という相続放棄についてはあまり知られていません。今回はどのような場合に相続放棄をするとどうなるのか、判断の目安、また手続きのしかたなど、相続放棄についてお知らせいたします。
「相続放棄」の基礎知識 ―期限、判断基準、手続きなどの注意点
相続放棄とは
相続放棄とは、相続や受遺(後述)する権利を放棄して、財産を一切相続しないことです。相続や受遺を自ら放棄するという選択をする理由はさまざまです。生前の被相続人との関係や、他の相続人との関係で相続放棄を選ぶ場合もあるでしょう。また自営業などの場合には、その事業を継続させるために相続財産を特定の相続人に集める必要が生じて、他の相続人が納得したうえで相続放棄をする場合もあります。しかし相続放棄を選ぶ理由で最多のものは被相続人の作った負債を相続することを避けるためです。これは相続という行為が持つ特徴によって起こります。
相続と聞くと、不動産や預貯金など価値あるものを相続するイメージが強いでしょう。これらの価値のある相続財産を「プラスの相続財産」と呼びます。一方で被相続人が生前に契約した車のローンや借金、クレジットカードの未払い残高、連帯保証人になっていた場合の債務なども相続財産です。こうした借金や債務は「マイナスの財産」と呼ばれます。相続とは、この「プラスの財産」と「マイナスの財産」を一括して相続することです。プラスの財産だけを相続するということはできません。
このため相続人が相続財産の全体図を把握せず、相続をしてみたらマイナスの財産だけが残った、つまり借金の返済義務だけを負うことになる可能性もあるのです。このような結果を避けるためには、被相続人の死亡からできるだけ早い段階で相続財産の全体像をつかみ、相続がプラスになるのか、マイナスになるかの目算を立てることが大切です。
「受遺者」の相続放棄 ―「特定遺贈」と「包括遺贈」
相続放棄は、「法定相続人」または「受遺者」が行うものです。民法で定められた親族内の相続人が「法定相続人」、遺言によって遺産を受け取る(=受遺)ように指名された人が「受遺者」です。受遺者の場合は、被相続人が受遺者にどのように財産を贈る(遺贈する)と指定したかによって、相続放棄の手続きが異なります。
特定遺贈
例えば「Aさんには愛用した車を贈る」など、特定のものを指定している場合は「特定遺贈」と呼ばれます。この特定遺贈を受ける受贈者が相続放棄をしたい場合には、相続人の一人に相続放棄する意思を伝えれば相続放棄が可能です。期限も特に決まりがありません。
包括遺贈
その一方で例えば「Bさんには遺産の10%を贈る」など、特定のものではなく、遺産の割合だけを指定する場合は「包括遺贈」と呼びます。包括遺贈の受贈者が相続放棄をしようとする場合には、法定相続人と同じ手続きが必要です。
相続放棄をするとどうなるのか~メリットとデメリット~
相続放棄をするということは、一切の相続財産にまつわる権利を放棄することになります。では具体的に相続放棄をした場合はどうなるのか、メリットとデメリットを見ましょう。
相続放棄のメリット
債務から解放される
相続放棄をする最大のメリットがこれです。マイナスの財産も引き継ぐということは、被相続人に債務があった場合には相続人間で法定相続分に従って、債務も引き継ぐということです。被相続人が残した状態のまま引き継ぐので、借金の返済が滞っていた場合には遅延損害金や延滞料金も引き継ぎます。そしてこれらを相続したら債務者への返済をしなければなりません。相続放棄をすると、こうした債務から解放されます。
相続放棄のデメリット
すべての相続財産を手放すことになる
相続放棄のデメリットは、被相続人の財産を全て手放さなければいけないことです。仮に相続人と被相続人が、被相続人が所有する家に同居していた場合、相続放棄をしたら家は他の相続人のものになります。そのため相続放棄をした相続人は退去を迫られる可能性が高くなります。また被相続人の相続財産のうちで思い入れのあるものを相続することも一切あきらめなければなりません。
撤回や取り消しができない
相続放棄の手続きをとると、その手続きの後から思ってもいなかったプラスの相続財産が出てきて、マイナスの財産を相続しても余るほどのプラスの財産を相続できることになった場合でも、それを相続する権利はありません。相続放棄は撤回や取り消しができません。これも相続放棄のデメリットです。
相続財産や法定相続分について思い違いをしていたり、プラスとマイナスの財産の把握が間違っていたりした場合でも、相続放棄の撤回や取り消しなどができません。そのため、まずは相続財産について慎重に確認をして、下記の相続放棄を検討する場合にあたるかを参考にしながら相続放棄の手続きをすることが大切です。
他の相続人に影響する
ある相続人が相続放棄をすると、ほかの相続人に影響を与えます。これも相続放棄のデメリットです。例えば父が死亡し、法定相続人が子であるAとBとCの3人である場合を考えてみましょう。相続財産はトータルで大きくマイナスだったとします。
相続放棄は単独で手続きができますので、AはBやCの同意を得ること無く相続を放棄することも可能です。Aが相続を放棄すると、本来Aの分だったマイナス財産はBとCに移行します。結果的にBとCは予想していたよりも大きなマイナス財産を受け継がねばならず、Aが相続放棄した分のしわ寄せを受けてしまいます。
円滑な人間関係のためには、相続放棄を検討している段階から、AはBとCに「相続放棄をしようと思う」と打診しておく方がよいでしょう。事後通知で「相続放棄した」と聞かされた場合、他の相続人は事前の心づもりと違う分量のマイナス財産を受け継ぐので、感情的にこじれる可能性があるからです。次章も参照し、影響を与える相続人にできるだけ事前の相談をしておくようにしましょう。
相続放棄をすると相続人が変わる
法定相続人には、配偶者と血縁関係による相続人がいます。そのうち血縁関係による相続人は下のような優先順位があります。
第1順位:子(または代襲相続人である孫など)
第2順位:直系尊属(父母、または代襲相続人である祖父母)
第3順位:兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪)
たとえば、被相続人に妻と子がいる場合には、通常は妻と第1順位の子が相続人です。仮に被相続人のマイナスの財産が大きいことを理由にして妻と子の全員が相続放棄をした場合を考えましょう。妻と子全員が相続放棄した場合には、相続権は第2順位の直系尊属、つまり父母または祖父母が生きていれば、その人に移ります。すなわちプラスとマイナス両方の財産を引き継ぐことになります。
第2順位の人がいない場合や、第2順位の人も全員相続放棄した場合には、第3順位の人、つまり兄弟姉妹や甥・姪が相続人になります。誰も借金を引き継がないためには第3順位の人も相続放棄をしなければなりません。第3順位までの人が全員相続放棄した場合には、それ以外の親族がいてもその人が相続人になることはありません。この場合には、相続人不存在ということになります。
このようにある順位の相続人全員が相続放棄をすれば、後順位の人が相続人になります。被相続人に大きなマイナスの遺産がある場合には、誰かがそのマイナスの遺産を引き継いでしまわないように全員で相続放棄をする方が賢明です。
相続放棄は順位ごとに
ただし、全員で相続放棄をしたい場合でも、異なる順位の相続人が同時に相続放棄の申述をすることはできません。先順位の相続人がいる場合には,先順位の相続人全員の相続放棄の申述が受理されてから、次順位の相続人が相続放棄の申述をします。
具体的には最初は配偶者+第1順位の子や孫、ひ孫が被相続人の死亡を知り自分が相続人であると知った日から3か月以内に相続放棄の手続きをします。これが受理されたら相続権が第2順位に移ります。
第2順位の人は、配偶者と第1順位の人全員の相続放棄が受理され、自分が相続人になったと知った日から3か月以内に、相続放棄の手続きをします。第2順位の人全員の相続放棄が受理されたら、相続権が第3順位に移ります。
第3順位の人は、第2順位の人全員の相続放棄が受理され、自分が相続人になったと知った日から3か月以内に、相続放棄の手続きをします。これが受理されれば、相続人全員の相続放棄が完了します。
相続放棄を検討した方がいいケース
相続財産を全て洗い出した段階で、下記のいずれかに該当する場合には相続放棄について検討する方がよいでしょう。
明らかにマイナスの相続財産がプラスの財産よりも大きい場合
マイナスの財産の方が明らかに大きいことが判明した場合には、債務だけを引き継ぐ可能性が高くなります。この場合には相続放棄を視野にいれて検討する方が賢明でしょう。
被相続人が誰かの連帯保証人になっている場合
連帯保証人と単なる保証人の立場は大きく違います。連帯保証人は資金を借りた債務者とまったく同様に、資金を貸した債権者から請求を受け、返済をしなければならない立場です。そのため被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合に、その連帯保証をした相手が債務の返済を滞らせていた場合には、被相続人が返済の義務を負います。従って被相続人の財産を相続すると、相続人にも債務を返済する義務が発生します。特に債務の金額が大きい場合には相続放棄を検討する方が賢明でしょう。
被相続人や他の相続人と関わりたくない場合
何らかの理由で生前の被相続人との関係がよくなかった、またはほかの法定相続人と関わりたくない場合には、相続放棄をすることも一つの選択肢となるでしょう。
自営業などの場合で、特定の相続人に相続財産を集中させたい場合
自営業などの場合、事業を承継する人に多くの財産を集中させたい場合があります。その場合には他の法定相続人が納得したうえで、相続放棄をする場合もあります。
相続放棄をするかどうか判断のポイント
相続放棄をすると債務から逃れることができます。けれどもいったん相続放棄の手続きをしてしまうと撤回や取り消しができず、プラスの財産も含めて一切の相続財産を受け取れなくなります。相続財産の中に債務があるから、という理由だけで相続放棄を決めては後で後悔することになりかねません。相続放棄するかどうかは慎重に判断しましょう。相続放棄をするかどうか判断のポイントを2つご紹介します。
借金などマイナスの財産とプラスの財産のバランスはどうか
借金などマイナスの財産額が多い場合には、プラスの財産を相続しても穴埋めできない可能性があります。最悪の場合には、ご自分の資産を使っても債務が残ってしまい、ご自身の経済的状況が悪化することになります。
一方でマイナスの財産額が大きくても、プラスの財産もまた多い場合には、プラスの財産でマイナスの財産を返済することが可能です。相続した不動産を売却し、その売却代金によって借金を返済することもできます。このように相続放棄をするかどうかの判断には、マイナスの財産額だけでなく、プラスの財産額とのバランスを確認することが大切です。
被相続人の相続財産の中に、思い入れのあるものがある場合
相続放棄をすると一切の相続ができなくなります。そのため被相続人の残した相続財産の中に相続人にとって思い入れのあるものが存在する場合には、相続放棄をするか、それとも相続放棄をしないで「限定承認」(後述、「相続放棄をする場合の注意点」の6.を参照)の制度を利用することも検討する必要があります。
相続放棄には手続き期限がある
相続放棄を検討する時に気を付けるべき点は、相続放棄の手続きには期限があることです。期限は被相続人が死亡して自分が相続人になったことを知った日(これを「相続の開始を知ったとき」といいます)から3か月以内です。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができません。
3か月以内と聞くと「まあそこそこ時間があるかな」と思われるかもしれません。しかし実際には葬儀のお返しの手配や法要や供養など、他にもしなければならないことがたくさんある時期です。その中で相続の開始を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きを終了させようとすると、3か月は意外に短い時間です。3か月の期限内に相続放棄の手続きを済ませるためには、被相続人が死亡した日からできるだけ早い段階で相続財産全体を把握する作業を始めましょう。そのうえで相続放棄をするかしないかの判断をして、期限に間に合うように相続放棄の手続きを始めましょう。
相続放棄の手続き
相続放棄全体の流れ
相続放棄の手続きとはつまり、家庭裁判所へ「相続放棄の申述を提出する」ということです。この際に必要書類も一緒に提出します。この手続きは被相続人の死と自分が相続人になったということを知ったとき(=相続の開始を知ったとき)から3か月以内に行わなければなりません。そして家庭裁判所から『相続放棄申述受理通知書』が届くと、相続放棄が完了します。「相続放棄の申述を提出する」までの流れを見ていきましょう。
相続財産を調査する
相続財産の全体像を把握するために、プラスとマイナス全ての相続財産を調査します。相続の開始を知ったときからだいたい1か月程度を目安に終えるようにしましょう。この際に、財産目録を作っておくことをおすすめします。相続放棄の申述書にも財産状況を記載しますし、仮に相続放棄をせずに遺産分割協議をすることになった場合でも、役に立つからです。
相続財産の調査方法については、以下の記事をご参考にしてください。
申述に必要な書類を作成し集める
相続放棄をすると決めたら必要な書類を準備します。相続放棄をする人(以下、申述人)と被相続人との親族関係により、用意する書類は異なりますが、以下は全員共通で必要な書類です。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
さらに申述人と被相続人の関係によってどのような書類が必要なのかをみましょう。
申述人が被相続人の配偶者の場合
上記1.~3.に加えて
4. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
1.~4.に加えて
5.申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人、つまり被相続人の子や孫)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
1.~5.に加えて
6. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 被相続人の直系尊属に死亡している方(例:申述人が祖父母の場合には、それ以前に相続権がある被相続人の父母)がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
上記1.~8.に加えて
9. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
10. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人、つまり被相続人の兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
このように第二順位相続人からは、被相続人が生まれてから死ぬまでを辿れる戸籍が必要になります。遠方の場合郵送で請求します。さらに本籍を転々と変えている場合には、それだけ取り寄せる戸籍関係の書類が多くなります。そのため書類を手に入れるだけで思いもかけず時間がかかります。また相続放棄に必要な書類に不備があると期限内の申し立てに間に合わなくなるので、必要書類の収集は早く始めましょう。
家庭裁判所に相続放棄の申述を提出する(相続放棄の申立てをする)
相続放棄の申述を提出するのは、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。必要書類とともに提出します。原則的に相続人本人が行いますが、相続人が未成年である場合は法律行為ができませんので、その親などの法定代理人が申し立てます。申述書を提出した後に家庭裁判所から必要に応じて他の書類提出の連絡が来る場合もあります。その都度指示に従ってください。
家庭裁判所から照会書が届く
家庭裁判所に相続放棄を申立てると、約10日後に相続放棄に関する照会書が送付されます。送付書には回答を記入するところがありますので、必要事項を記入して家庭裁判所へ返送しましょう。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を返送した後、10日間ほどで家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。これにより相続放棄が正式に認められます。
申述書の用紙や記入例などについては下記の裁判所のページを参考にしてください。
相続放棄をする場合の注意点
1. 申し立ての期限
繰り返しになりますが、相続放棄の申し立ては被相続人が亡くなり、自分が相続人と知ったとき(=相続が開始したとき)から3か月以内という期限内でないと原則受け付けられません。そのため逆算をして、早めに準備をすることが何よりも大切です。
なお先順位の相続人がいる場合には,先順位の相続人全員の相続放棄の申述が受理されてから次順位の相続人が相続放棄の申述をします。
具体的には最初は配偶者+第1順位の子や孫、ひ孫が、被相続人の死亡を知り自分が相続人であると知った日から3か月以内に相続放棄の手続きをします。これが受理されたら相続権が第2順位に移ります。配偶者と第1順位の人全員の相続放棄が受理され、自分が相続人になったと第2順位である直系尊属、つまり父母または祖父母にあたる人が知った日から3か月以内に、第2順位の人が全員で相続放棄の手続きをします。
この時点で、既に被相続人が死亡してから3か月を超えていても、第2順位の人が相続放棄の手続きをとることは可能です。なぜなら第2順位の人は仮に被相続人の死亡を知っていても「配偶者と子供という先順位の相続人がいるので相続はそちらでするだろう」「まさか自分が相続人になるなんて思わなかった」という事情が十分に考えられるからです。
相続放棄を申し立てる期限は、「被相続人が亡くなったと知った+自分が相続人と知った」という2つの要素を共に知った時から3か月以内です。
2. 相続放棄の申し立ては1回だけしかできない
一度申し立てをして、何らかの理由で家庭裁判所から相続放棄を却下された場合には、たとえ申し立ての期限3か月以内であっても、再度申し立てすることはできません。そのため、相続放棄の申し立てをする場合には、却下されないように細心の注意を払って必要書類を作成、準備しましょう。
3. 法定単純承認をすると、相続放棄はできない
民法921条の規定により、相続人が以下の3件を行うと、相続を承認したとみなして(これを「法定単純承認」といいます)相続放棄ができなくなります。
- 相続財産の一部または全部を処分した
- 相続が開始した日から3か月以内に相続放棄の手続きをしなかった
- 相続財産を故意に隠ぺいした
4. 相続放棄は親族に伝えただけではできない
相続放棄手続きは、親族に口頭または文書で伝えておけばよいということはありません。「遺産分割協議で全ての財産の相続を放棄すると宣言し、その旨を遺産分割協議書に書いた。相続人全員が納得をして署名捺印したら大丈夫」と思われるかもしれませんが、これは債権者に対しては全く効力がありません。
相続放棄をするということは、「相続人が遺産の相続全てを放棄することを家庭裁判所へ申し立て、受理されること」です。自筆で「相続放棄をする」と書いても、相続放棄をしたことにはなりません。
5. 相続放棄手続きは郵送のみでも可能な場合も
相続放棄の申し立ては、必要な書類が全て揃っていれば郵送でも可能です。ただし、家庭裁判所によっては郵送では受け付けない場合もありますので、事前に被相続人の最後の住居地を管轄する家庭裁判所へ電話などで問い合わせをすることをおすすめします。また裁判官が審理をするにあたって面接などを求めてきた場合は従わなければなりません。その場合は裁判所へ出向く必要があります。
6. 相続放棄の判断が難しい場合は「限定承認制度」の利用も検討する
プラスの財産とマイナスの財産のどちらのほうが多いのかはっきりしない場合は「限定承認制度」を利用することもできます。
限定承認とは、相続する人がプラスの財産の範囲内でプラスとマイナス両方の財産を引き継ぐ制度です。仮に莫大なマイナス財産があっても、そのマイナス財産全体を引き継ぐのではなく、プラスの財産分と同等のマイナス財産だけ引き継げばよいのです。金銭的にはプラスマイナスゼロになる可能性もありますが、マイナス財産だけが残る、という事態は避けられます。またよく調べてみたら大きなプラスの財産があり、マイナスの財産を清算しても余りが出たら、それを相続することも可能です。
とても便利そうな制度ですが、この限定承認制度はすべての相続人が「共同」で行わなければならず、清算手続きが煩雑になり、さらに被相続人の準確定申告が必要になるなど使いにくい制度でもあります。相続放棄は各相続人が単独で行えますので、相続人全体の合意がとれれば限定承認、取れない場合は相続放棄を考えるとよいでしょう。
7. 相続放棄と生命保険金や遺族年金の受け取りについて
相続放棄をして、被相続人が所有していた一切の相続財産を引き継ぐ権利を失った場合でも、相続人を受取人とした生命保険金や遺族年金の受け取りは可能です。
そもそも受取人が指定されている生命保険金と、受給権者を遺族と定めている遺族年金は、生命保険の受取人と遺族年金の受給権者、それぞれの固有の財産です。これらは相続財産に含まれません。そのため、相続人が相続放棄をしても生命保険金と遺族年金の受け取りは可能です。
ただし生命保険の受取人が被相続者だった場合には、注意が必要です。生命保険金はいったん受取人である被相続人に支払われ、あらためて相続人へ相続された、とみなされます。そのため死亡保険金を受け取ってしまうと、民法で定める「法定単純承認」に該当してしまうので相続放棄ができなくなります。
8. 相続放棄を原因とする場合、代襲相続は発生しない
相続放棄をした場合には、その相続人は初めから相続権を持っていなかったことになります。この場合には相続人が死亡していた場合と異なり代襲相続はできません。
9. 被相続人が税金などを滞納したまま亡くなった場合
相続放棄をした場合、原則として滞納した税金の支払いは免除されます。被相続人の死亡した年の所得税は、相続放棄をした場合には払う必要はありません。また、被相続人が数年分の所得税を滞納していたとしても滞納した所得税を支払う必要はありません。
一方注意が必要なのは市民税と固定資産税です。これらはその年の1月1日時点で住所がある、または保有している人が納税者となります。従って1月1日の時点で相続放棄が認められていなければ、故人名義で納税に関する通知が送られてきます。そこで1期分でも税金を支払ってしまうと、相続したとみなされてしまいますので、支払わないように気を付けましょう。相続放棄が認められ受理されると、相続開始日に遡求して相続人でないことなりますので、市民税や固定資産税も相続放棄できます。
また、国民健康保険税についても被相続人の滞納分の支払いは免除されます。
10. 相続人全員が相続放棄をした場合
親族全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、相続財産を管理する人がいなくなります。この場合には家庭裁判所に申立てをし、相続財産管理人を選任してもらうことができます。
相続財産管理人は、相続財産をお金に換え、債権者に弁済する手続きなどを行います。最終的に残った財産があれば、相続財産管理人は、その財産を国庫に帰属させます。
11. 相続財産の管理責任
相続放棄をすれば相続人ではなくなりますが、相続財産の管理義務がなくなるわけではありません。相続放棄をした人は、次に相続人になった人が相続財産の管理を始めることができるまで、相続財産の管理を継続しなければなりません。
なお、相続人全員が相続放棄をして次に相続人になる人がいない場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。そして相続財産管理人が選任されるまでは、相続人が管理責任を負います。
まとめ
相続ということ自体が人生で稀なできごとです。親しい人を失った悲しみや葬儀や法要をしながら、相続について考えるのは大変なことです。けれどももし被相続人に大きなマイナスの財産があった場合には、相続放棄をしないとその大きなマイナスの財産、例えば借金などの債務を相続することになります。はたして被相続人はそれを望んでいるでしょうか?
マイナスの財産など残したくはなかったけれど、残ってしまった。だけど相続人には「相続放棄」という手段を選んで、債務から解放されて欲しいと願っているかもしれません。被相続人の死亡から3か月以内という短い期間に手続きをすることは容易ではありませんが、この記事をご参考に、よりよい判断をくだし、実行されることをおすすめいたします。
行政書士・FP 田中真作
相続や離婚などの一般市民法務相談や各種許認可業務など幅広く対応。
田中真作のFacebookページ https://www.facebook.com/shinsaku.tanaka.9