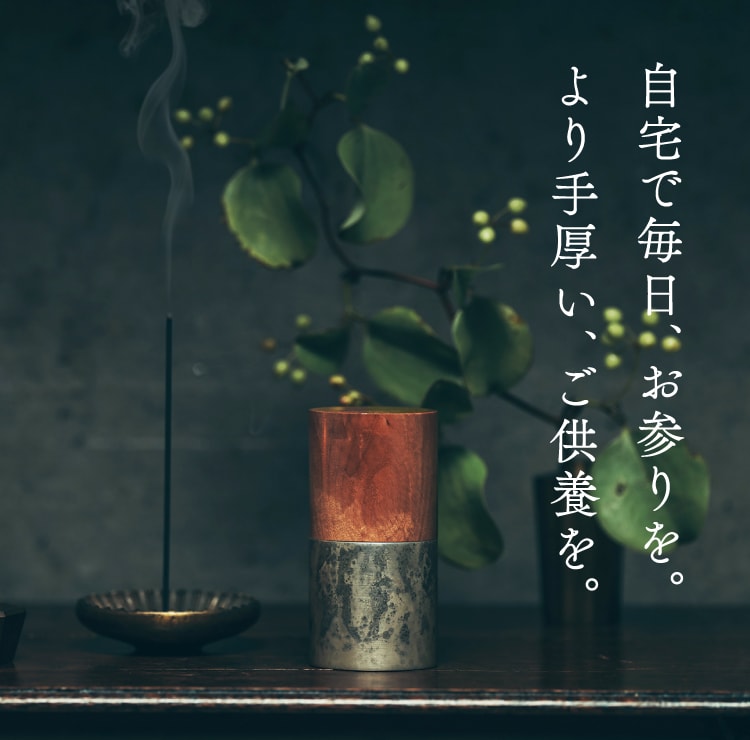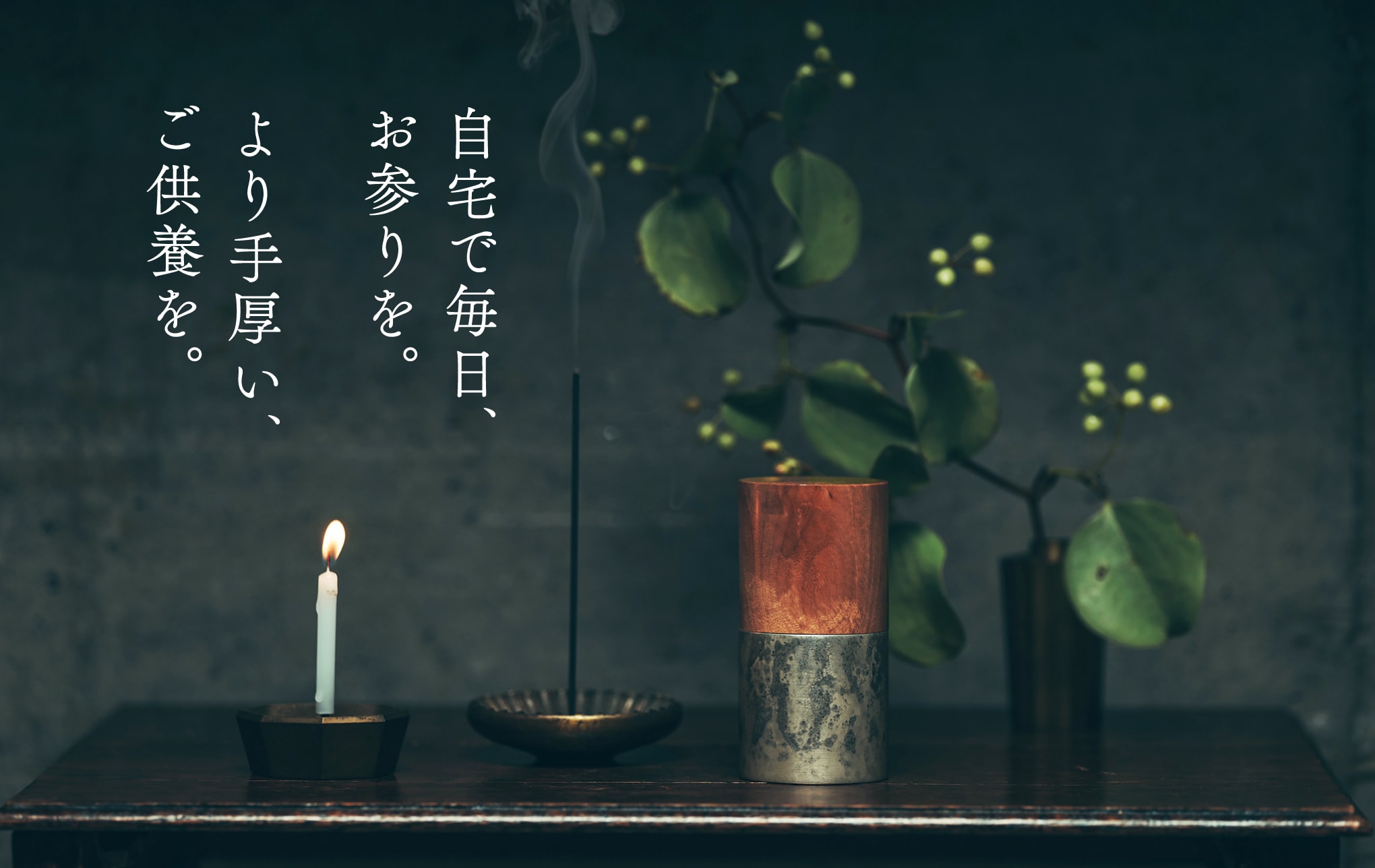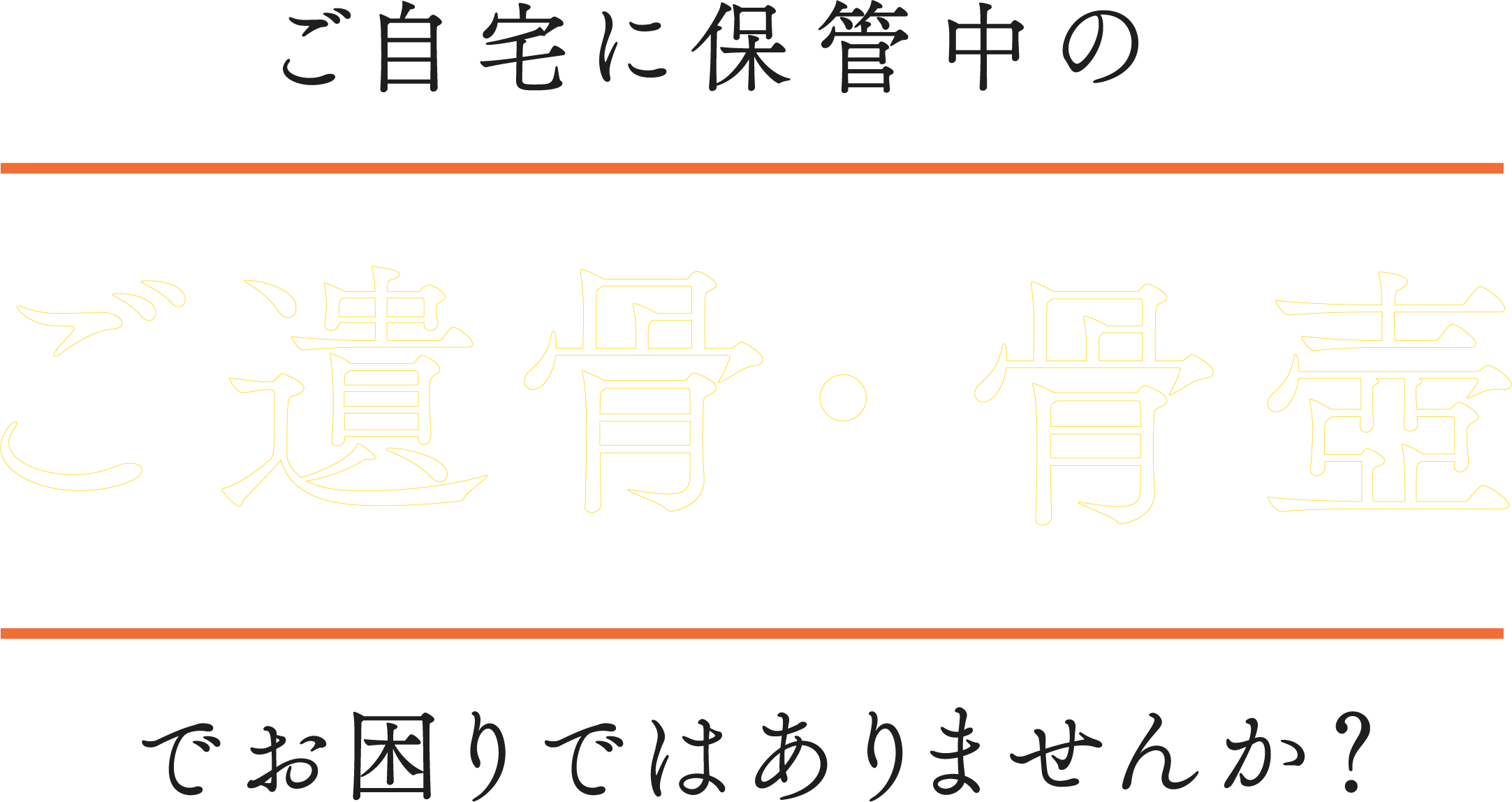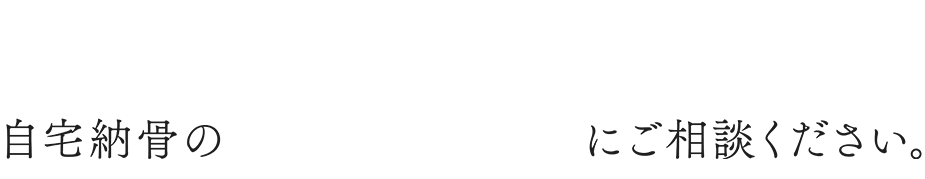葬儀が終わって気持ちが落ち着き始めたら、遺品の整理をしなければなりません。遺品の中でも生前とくに大切にしていた持ち物は「形見」となり、故人のことが思い出される品となります。今回は「形見分け」についてくわしく紹介します。「形見分け」とは、故人と縁のあった方に形見を分配することです。形見分けが原因でトラブルになるケースもあるため、注意点や行う時期などくわしくチェックしましょう。
形見分けの行い方 時期や気をつけるべき注意点
1.形見分けについて
「形見分け」は日本で古くから行われてきた慣習のひとつです。どのような行いか、くわしくチェックしましょう。
形見分けとは
生前に故人が愛用していた品を、親族やとくに親しくしていた友人などに分けることを「形見分け」といいます。見ると故人のことが思い起こされるような品を「形見」として選び、分配することで、遺品を通して故人との思い出を共有することができます。
形見分けは、必ずしなければならないものではありません。「だれに何を渡さなければならない」という決まりはないので、年齢や好み、共通の趣味などに応じて品物を選ぶといいでしょう。
形見分けと遺品整理とのちがい
亡くなった人の遺品を整理する「形見分け」と「遺品整理」ですが、内容や目的は大きく異なります。
- 形見分け:故人ととくに縁のあった人へ遺品を分配し、故人をしのび供養する。
- 遺品整理:遺品や遺産を整理したり処分したりすることで、家の中を整理する
時期
形見分けを行う時期に決まりはありませんが、遺族が故人の冥福を祈り喪に服す期間を終える「忌明け」以降に行われることが多いようです。親族や故人と親しくしていた人が集まる機会などに形見分けをするといいでしょう。
宗教により忌明けの時期は以下のように異なります。
- 仏教:四十九日法要の後
- 神道:三十日祭または五十日祭の後
- キリスト教:追悼ミサ(カトリック)、召天記念祭(プロテスタント)後(どちらも亡くなってから1か月経つと行われる)
キリスト教には本来「忌明け」という概念や、「形見分け」というしきたりはありませんが、日本では形見分けが行われることも多いようです。
形見は遺産として相続対象になるため、法定相続人の財産になります。とくに資産価値のありそうな遺品の形見分けは、注意が必要です。
相続協議を終える前に一部の相続人の判断で勝手に形見分けを行った結果、遺族間でのトラブルに発展するケースもあるのです。資産価値のありそうな遺品に対しては、相続人全員の同意がされており、相続に関する協議を終えてから形見分けを行いましょう。
また「故人と親しかったから」「親戚だから」といって、法定相続人の同意なしに勝手に形見を持ち帰ることもいけません。
2.形見分けの行い方
形見分けの方法には決まりがありませんが、ポイントを紹介します。
エンディングノートのチェック
遺品の整理の仕方について、エンディングノートに故人が希望を記している場合があります。エンディングノートがある場合は、形見分けについての記載があるかチェックしてみましょう。
形見分けリストを作る
遺品整理をする際に形見分けをする品物のリストを作っておくのがおすすめです。渡し間違いや勘違いなどのトラブルを防ぐことができます。
品物の選び方
形見分けで贈る品物は高価なものでなければ、とくに決まりはありません。相手が喜びそうなものや故人との思い出の品、共通の趣味のものを渡すといいでしょう。
具体的には衣類、かばん、時計、文具、家具、アクセサリー、書籍、写真などです。受け取った人が喜び、大切にしてくれるように、クリーニングや動作確認をするなど良い状態で渡すようにしましょう。
ただし、「現金や金券などお金が絡むもの」は財産分与に相当します。また後述するように、贈与税や相続税の控除額以上の資産価値になるものを形見分けする場合は、注意が必要です。
「免許証や契約書などの重要書類」などもトラブルに発展する恐れがあるため、形見分けしないようにしましょう。
「故人が飼っていたペット」を形見分けとして、突然渡すと受け取った人は困ってしまいます。事前に故人と引き取ることを約束していたり、本人が引き取りを希望したりしない限りは、遺族が引き取りましょう。
渡し方
形見分けはプレゼントではないので、品物を包装する必要はありません。半紙などで軽く包んで渡すといいでしょう。
相手が遠方に住んでいる場合は郵送しても構いませんが、ていねいな手紙を添えて送りましょう。
3.形見分けの注意点・マナー
故人をしのぶために行う「形見分け」ですが、トラブルに発展するケースもあります。注意しておきたいポイントやマナーを確認しましょう。
良い状態のものを渡す
形見分けをする品は、良い状態にお手入れをしてから相手に渡しましょう。たとえば「衣類を渡す場合はクリーニングをする」「傷んでいるもの・安すぎるものは渡さない」「貴金属やアクセサリーはきれいに磨いてから渡す」などの配慮が必要です。また相手の趣味や好みを考えて、喜んでもらえるものを渡しましょう。
無理に渡さない
形見分けは不要なものを相手に押し付けるというものではありません。たとえ遺族にとっては思い出の品でも、受け取る側にとってはそうでない場合もあります。形見分けを相手が遠慮されたら、遺品を押し付けることはやめましょう。
相続放棄している場合は形見分けできない
形見を受け取るという「形見分け」は相続または贈与に当たります。相続人が形見分けとして多くの遺品を持ち帰った場合は、相続を承認したとみなされます。相続放棄しているにもかかわらず形見を受け取った場合は、相続放棄が無効になるケースもありますので気をつけましょう。
「資産価値がないものであれば相続には当たらない」とされるケースもありますが、線引きが非常に難しいため、相続放棄する場合の形見分けは弁護士などの専門家に相談しながら行いましょう。
相続税や贈与税がかかる場合もある
宝石や貴金属などの高価な品を受け取った場合は、相続税や贈与税を払う必要があるかもしれないので注意が必要です。
【相続人が形見を受け取る場合】
たとえ「形見分け」という名目であっても、市場価値があると判断された遺品を相続人が受け取る場合は、相続税が課される可能性があります。
ただし相続税には「基礎控除額(※)」があります。基礎控除額を超えない場合は申告の必要がありません。基礎控除額を超える財産がある場合は相続税対象となるので注意しましょう。
【相続人以外が形見を受け取る場合】
相続人以外の人が高価な品を形見として受け取った場合は、贈与税の対象となります。
ただし贈与税は年間110万円までであれば課税控除されます。110万円を超える品を形見分けされた場合は、贈与税の対象となるので注意しましょう。
目上の方への形見分け
昔から形見分けは故人の親族や親交のあった友人へ渡すのが一般的で、目上の方へ形見を贈ることは失礼とされてきました。故人が使用した古いものを故人よりも目上の人に差し上げるべきではないと考えられてきたためです。最近では故人より年上でも親しい人には形見分けをするケースもありながら、いっぽうでしきたりを気にする方もいるようです。目上の方への形見分けは、故人とその方の関係性も鑑みながら検討するようにしましょう。
4.形見分けにお礼は必要か?
形見分けをされた場合のお礼は基本的には不要です。どうしてもお礼をしたい場合は、お墓や仏壇にお花や果物、線香、ろうそくなどをお供えするといいでしょう。