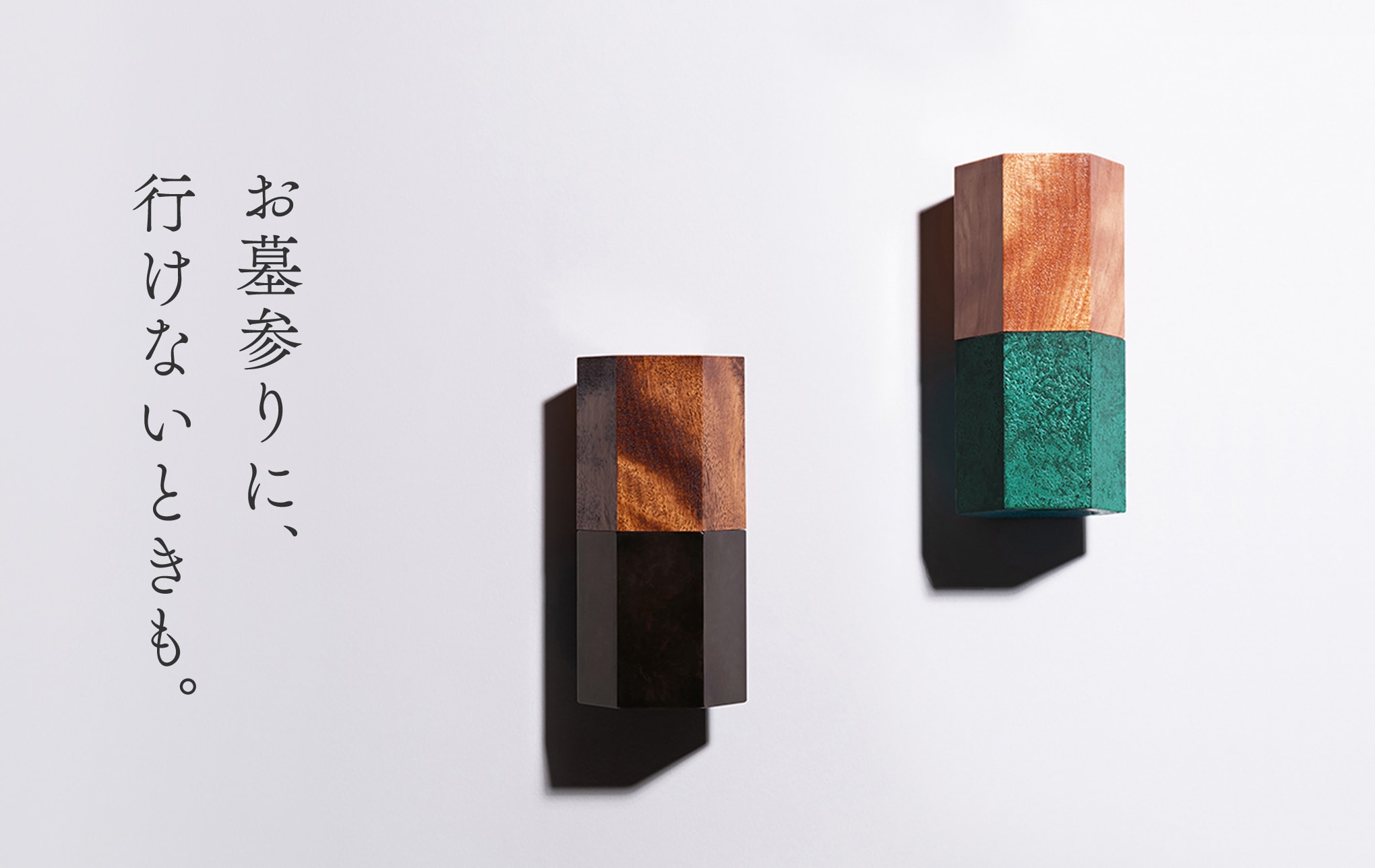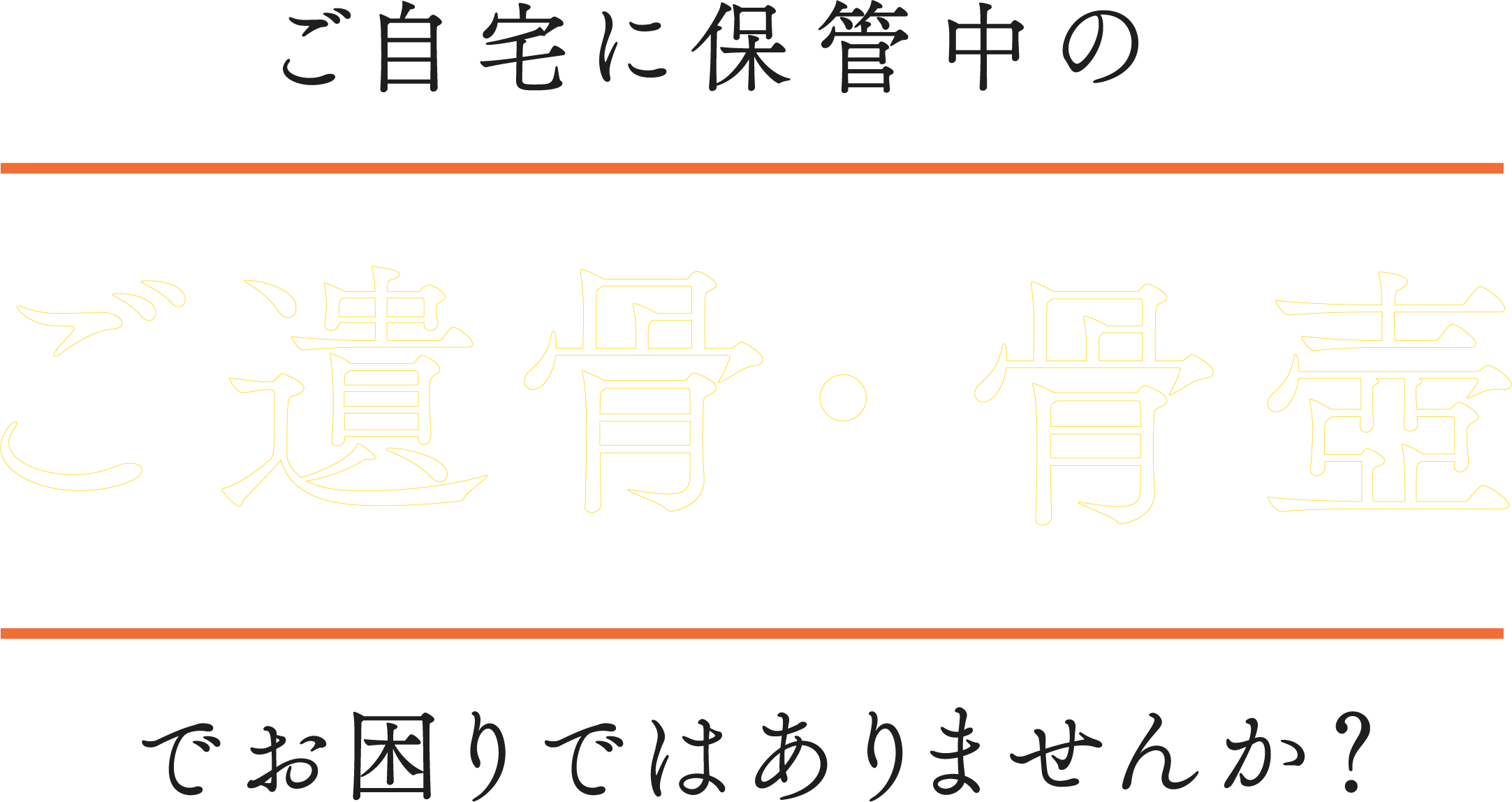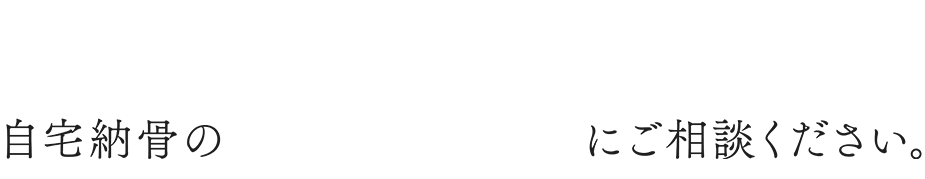相続財産と相続税課税対象のフクザツな関係
相続手続きの初期段階に相続財産の確認と評価額を決める作業があります。
相続財産と相続税の課税対象の関係は「相続財産(だけ)=相続税の課税対象」と理解されやすいのですが、これは誤りです。実際の関係は「相続財産<相続税の課税対象」です。相続財産とは何か、を決めているのは民法ですが、民法は相続税の課税対象を決めていません。相続税の課税対象は相続税法という別の法律によって決められています。
この2つの法律が決めている範囲が異なるため「相続財産(だけ)=相続税の課税対象」と考えていると、想定していなかったものが相続税の課税対象となる可能性があります。すると相相続税の計算をやり直す必要がでてきたり、相続税の課税対象申告漏れを指摘されることもあります。
相続税の課税対象になるもの
「相続財産<相続税の課税対象」ならば、相続税の課税対象となるものは何でしょうか?いわゆる「相続財産」も含めて、相続税の課税対象になるものの全体像を把握しましょう。
1. 本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が生前持っていた財産の権利義務のうち、相続または遺贈(=遺言により相続人、または相続人以外の人や団体に無償で財産を分け与えること)により相続人または受遺者(=遺贈を受ける人や団体)が受け取る財産を言います。
相続税法ではこのうち金銭に見積もることができる、経済的価値のあるもの全てを相続財産として扱います。さらに民法の「相続財産」にはプラスもマイナスもありましたが、相続税法ではプラスの財産のみを「相続財産」としています。マイナスの財産は一旦「相続財産」から切り離して考え、最終的に課税価格を計算する時に「債務」としてマイナスします。
また実質的には被相続人の管理下にあった未登記の土地建物や、被相続人以外の家族や他人名義の預貯金なども相続財産に含まれます。例えば孫名義の銀行口座残高も、名義は孫であっても実質的にそこに入金していたのが被相続人であれば、被相続人の財産です。
2. 「みなし相続財産」
「みなし相続財産」とは民法上の相続財ではないけれども、相続税法上では相続財産とみなして相続税の課税対象になる財産です。典型的な例は生命保険金や死亡退職金です。これらは非課税枠が設定されています。
主なみなし相続財産
| 財産の種類 |
関係法令 |
規定要旨 |
| 生命保険金 |
相続税法3-1-1 |
それぞれの財産を相続または贈与により得たとみなす |
| 死亡退職金 |
相続税法3-1-2 |
| 生命保険契約に関する権利 |
相続税法3-1-3 |
| 定期金に関する権利 |
相続税法3-1-4 |
みなし相続財産については以下の記事もご覧ください。
他のみなし相続財産
主なみなし相続財産以外にも、みなし相続財産はあります。当てはまる方は少ないかもしれませんが、下の一覧をご参考にしてください。すでに主なみなし相続財産としてご説明したものは除いています。
| 財産の種類 |
関係法令 |
規定要旨 |
| 保証期間附定期金に関する権利 |
相続税法3-1-五 |
それぞれの財産を相続または遺贈により得たとみなす。 |
| 契約に基づかない定期金に関する権利 |
相続税法3-1-六 |
| 特別縁故者に対する相続財産の分与 |
相続税法4 |
与えられた時のその財産の時価相当の金額を遺贈により得たとみなす。 |
| 低額譲受(=遺言により著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合) |
相続税法7 |
その対価と時価との差額に相当する金額を遺贈により得たとみなす。 |
| 債務免除等(=遺言により対価を支払わずに、または著しく低い価額の対価で債務を免除などされた場合) |
相続税法8 |
その免除された債務の金額に相当する金額を遺贈により得たとみなす。 |
| その他の利益の享受(=遺言により対価を支払わないで、または著しく低い価額の対価で利益を得た場合) |
相続税法9 |
その時の利益の金額に相当する金額を遺贈により得たとみなす。 |
| 信託に関する権利(=遺言などにより委託者以外のものが受ける信託の利益権利) |
相続税法9の2~9の6 |
その利益を受ける権利を遺贈により得たとみなす。 |
| 相続時精算課税適用者(相続または遺贈により財産を取得しなかった者)の受贈財産 |
相続税法21の16-1 |
その財産を相続または遺贈により得たとみなす。 |
| 特別の法人から受ける権利(=財産の贈与または遺贈により持分の定めのない法人から利益を得る権利) |
相続税法65-1 |
財産の贈与または遺贈により受ける利益に相当する金額を、財産を贈与または遺贈した人から贈与または遺贈により得たとみなす。 |
| 贈与税の納税猶予の適用を受けていた農地等(贈与者が死亡した場合) |
措置法70の5 |
その農地等を相続または遺贈により得たとみなす。 |
| 贈与税の納税猶予の適用を受けていた非上場株式等(贈与者が死亡した場合) |
措置法70の7の3 |
その非上場株式等を相続または遺贈により得たとみなす。 |
3. みなし相続財産ではないが相続税課税価格の計算に加えるもの
相続時精算課税適用者の受贈財産
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時に、相続税を計算する際に相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します(相続税法21の15-1)。
相続開始前3年以内の贈与財産(=贈与を受けた財産)
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与をされた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に、過去3年以内に贈与をされた財産の贈与の時の価額を加算します。これを「生前贈与加算」や「贈与額持ち戻し制度」と呼びます。
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものが対象になるので、3年以内であれば既に贈与税を支払っていても相続財産に加算します。さらに基礎控除額110万円以下の贈与財産や、死亡した年に贈与されている財産の価額も加算します。ただし加算された贈与財産に対して既に支払った贈与税額は、加算された人の相続税の計算で控除されます。
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の管理残額
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に父母や祖父母(=以下「贈与者」)から20歳から50歳未満の子(=以下「受贈者」)が結婚や子育てのための資金を受け取った場合、金融機関で所定の手続きをすると1,000万円までの資金に対して贈与税がかかりません。
しかし受贈者が50歳になるまでの契約期間中に、贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額(=1,000万円)から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円が限度)を控除した残額(以下「管理残額」)を、贈与者から相続等により得たとされ、相続税の課税対象になります(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)。
父母などからの教育資金の一括贈与を受けた場合の管理残額
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の人(以下「受贈者」)が、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」)から教育資金に充てるために受け取った金銭などのうち1,500万円までは、金融機関で所定の手続きをすると贈与税がかかりません。
しかし受贈者が30歳になるまでの契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として死亡日における非課税拠出額(=1,500万円)3から教育資金支出額 (学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)を控除した残額のうち、贈与者の死亡前3年以内に非課税制度に該当して受け取った金額は、贈与者から相続等により得たとされ、相続税の課税対象になります。
ただし贈与者の死亡日に受贈者が23歳未満である場合や、平成31年4月1日以後に取得した信託受益権又は金銭等がない場合など、一定の場合には相続等により取得したこととされません(所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)。
相続税の課税対象にならない「非課税財産」とは
相続または遺贈により得た財産(みなし相続財産を含む)でも、以下のものは相続税の課税対象ではありません。これらを相続税の非課税相続財産と呼びます。
相続税の非課税財産の種類
相続税法と措置法で定められた非課税財産のうち、一般に、
- お墓、墓石や祭具など、またこれに準ずるもの(相続税法12-1-一)
- 一定の公共事業を行うものが取得した公益事業用財産(相続税法12-1-二)
- 相続人が取得した生命保険期のうち一定の金額(=非課税枠)(相続税法12-1-五)
- 相続人が取得した退職手当金等のうち一定の金額(=非課税枠)(相続税法12-1-六)
- 相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人または認定特定非営利活動法人に贈与(寄付)した財産(措置法70)
- 学校法人ではなく、5年以上継続している個人経営の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教育用財産(不動産や事務用品、現金や預金も含む)は、当分の間非課税とされます(相続税法施行規則附則4,5,6)。ただし相続人が事業を継承し、引き続き事業を行う必要があります。
- 各種贈与の贈与税非課税枠内金額
以上が相続税の非課税となります。
お香典は被相続人の財産ではないので、相続税の課税対象にはなりません。ただし社会通念を大きく超える額のお香典の場合には、贈与税課税対象とみなされる可能性があります。
相続税課税価格の計算方法概略と相続税課税対象額計算例
各相続人及び受遺者の相続税課税価格の計算方法概略
本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税適用財産―債務及び葬式費用+被相続人からの3年以内の贈与財産=相続税課税価格
この計算式で各人の課税価格を計算します。さらに各相続人や受遺者全員分の相続税課税価格を合計したものが、課税価格の合計額となります。
なお相続税が課されることになった過去3年以内の贈与については、既に支払った贈与税がある場合には上で計算した相続税課税価格に対する相続税額から、既に支払った贈与税の額をマイナスして納税します。
相続税の基礎控除額
相続税を計算する際には基礎控除があります。
相続税基礎控除額の計算式
相続税基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
ここで使う「法定相続人の数」は民法で定められた相続人の数で、相続税法で使う相続人の数ではありません。
計算例
例1:相続人がA,B,C 3人の場合
相続人Aの相続税課税価格1,000万円+相続人Bの相続税課税価格2,000万円+相続人Cの相続税課税価格1,500万円=相続人全体の相続税課税価格4,500万円(X)
基礎控除額:3,000万円+600万円×相続人の数3=3,000万円+1,800万円=4,800万円(Y)
相続税課税価格4,500万円(X)-基礎控除4,800万円(Y)=マイナス300万円
→ 相続税は非課税
例2:相続人がA,B,C 3人の場合
相続人Aの相続税課税価格1,500万円+相続人Bの相続税課税価格2,500万円+相続人Cの相続税課税価格2,000万円=相続人全体の相続税課税価格6,000万円(Z)
基礎控除額:3,000万円+600万円×相続人の数3=3,000万円+1,800万円=4,800万円(Y)
相続税課税価格6,000万円(Z)-基礎控除4,800万円(Y)=1,200万円
→ 相続税の課税対象
このように計算をしてみると相続税の支払いが必要か、支払いが無い(=非課税)かがわかります。相続税の支払いが必要なケースで実際に相続税がいくらになるかは、税務署へお問い合わせください。
まとめ
相続税の課税対象は本来の相続財産(=相続人が分け合う財産)より広く、特に「みなし相続財産」についてはよく調べないと、まさかこの金銭が相続財産になるとは思わなかった、ということになりかねません。悪意なく、みなし相続財産の一部を相続財産と考えずに相続税の申告をした場合でも、税務署から「過少申告」と指摘を受けるとペナルティが課されます。そのためプラスとマイナスの相続財産がだいたい把握できた段階で、相続税の課税対象になるものをリストアップすることをおすすめします。
受取人が指定個人の場合は(Aさん)など個人宛の遺産であることを明記しながら、まず基本となる「本来の相続財産」+「みなし相続財産」の合計額を算出します。
その後、相続時精算課税に該当するものがあるか、3年以内に贈与があったか、を調べていきましょう。債務にはお葬式の費用(ただしお香典のお返しや僧侶へのお礼、法要のふるまいは除く)も含まれます。
また相続税を最終的にまとめる際には各種の控除(小規模宅地等の特例、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者や障碍者控除など)があります。これらも計算に入れていきますので意外に手間がかかります。
いずれにしても相続税の申告・納税期限は相続が開始してから10ヶ月です。この期限を過ぎるとペナルティが課されます。相続税がかからない(=非課税)と計算結果が出ても相続税の申告はしなければいけません。申告をしないとこれもまた「無申告」ということでペナルティを課されてしまいます。実際に相続税を払うケースは、相続全体の8%程度ですが、慎重に迅速に計算をしていきましょう。
国税庁が「相続税の申告のためのチェックシート(令和元年分以降用)」を公開しています。これを手元におきながらチェックしていくと良いでしょう。不明な点やわからない点があったら、お近くの税務署にお問い合わせください。
監修
アイリス綜合行政書士事務所
行政書士・FP 田中真作